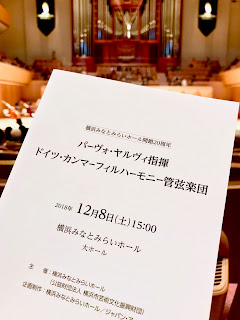2025-04-12 @NHKホール
パーヴォ・ヤルヴィ:指揮
NHK交響楽団
アントワーヌ・タメスティ:ビオラ*
ベルリオーズ:交響曲「イタリアのハロルド」*
プロコフィエフ:交響曲第4番ハ長調 作品112
(改訂版/1947年)
----------------------
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV1007(ビオラ版)から「前奏曲」*
期待のPヤルヴィ。常任指揮者時代はたいてい響きも音楽の構成感も引き締まった演奏に好感していた。
今日も、一部にそういう雰囲気を彷彿とさせたが、全体としては、弦が美しくなかった。これがN響?と合点の行かない響きだったが、何が問題だったか?
2曲とも演奏機会が極めて稀で、おそらく、両方とも生では過去1回しか聴いていない。
「イタリアの〜」では、驚くことに指揮者の下手に用意してある独奏者用スペースに独奏者がいない状態で演奏が始まった。え〜?どこにいるんだ?と思ったら下手のハープの右に立って弾き始めた。以下、舞台中央(本来の独奏場所)、上手コンバスの内側、下手ハープの左と変幻自在だ。
独奏者ご本人のアイデアだそうだ(各楽器との掛け合いもあったかららしい。)。
また、終楽章に弦楽四重奏が入ることは覚えていた。
前回神奈川フィルで聴いた際は、Vn2人とVcが舞台から消え、舞台上の独奏Vaと弦楽四重奏を演奏した。
しかし今回はそういうバンダ的な演奏ではなく、各楽器のうんと後ろのプルトの奏者が独奏ビオラと舞台上で四重奏を弾いたので、あれ、どこでやってるの?とうろうろしながら結局カーテンコールで気が付いた次第。
まあ、管弦楽作品としてはコリに凝った作品だけど、あいにく、面白くない。
プロコ4番。これも随分久し振りで、かつ、始まっても覚えのある旋律も出てこなくて、記憶は完全消失していた。
そして、序奏?がニョロニョロと頼りなく、もうここで、集中する気力を失った。
ま、2曲とも楽しめなかった最大の原因はN響の、特に弦の響に艶がなかったことだと思う。
タスメティのEncでバッハの無伴奏Vc組曲1番前奏曲を弾いたがこれはとても良かったな。
♪2025-047/♪NHKホール-03