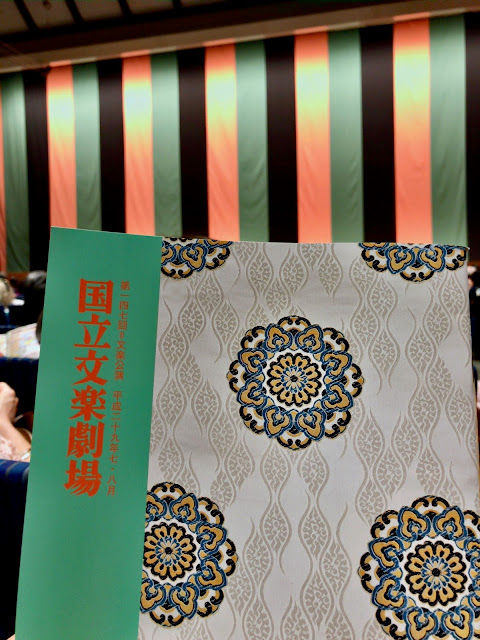本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)
●桔梗原の段
口 豊竹芳穂太夫/竹澤團吾
奥 竹本三輪太夫/竹澤團七
●吉田幸助改め五代目吉田玉助襲名披露口上
桐竹勘十郎・吉田簑助・(吉田幸助改)吉田玉男
吉田和生・吉田玉男・吉田簑二郎・吉田玉誉・
吉田玉勢・吉田玉志・吉田玉也・吉田玉輝・吉田玉佳
 ●景勝下駄の段
●景勝下駄の段竹本織太夫/鶴澤寛治
<襲名披露狂言>
●勘助住家の段
前 豊竹呂太夫/鶴澤清介
後 豊竹呂勢太夫/鶴澤清治
人形役割
高坂妻唐織⇒吉田簑二郎
越名妻入江⇒吉田一輔
慈悲蔵(直江山城之助)⇒吉田玉男
峰松⇒吉田簑悠
高坂弾正⇒吉田玉輝
越名壇上⇒吉田文司
女房お種⇒吉田和生
長尾景勝⇒吉田玉也
横蔵(後に山本勘助)⇒(吉田幸助改)吉田玉男
勘助の母⇒桐竹勘十郎(勘助住家<前>まで)
⇒吉田簑助(勘助住家<後>から) ほか
義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)
●道行初音旅
静御前⇒豊竹咲太夫
狐忠信⇒竹本織太夫
竹本津國太夫・竹本南都太夫・豊竹咲寿太夫・
竹本小住太夫・豊竹亘太夫・竹本碩太夫
竹本文字太夫
鶴澤燕三・竹澤宗助・鶴澤清志郎・鶴澤清馗・
鶴澤清丈・鶴澤友之助・鶴澤清公・鶴澤清胤・
鶴澤燕二郎
人形役割
静御前⇒豊松清十郎
狐忠信⇒桐竹勘十郎
吉田幸助という人形遣いはこれまでも何度か見ているが、顔と名前が一致しない。何しろ、人形使いはほぼ90%?が吉田某で残りの多くが桐竹某で、わずかに豊松という名がある。これは太夫、三味線でも同じ傾向だから姓・名を覚えるのは容易ではない。ついでに言えば、太夫は全員が○○太夫という名前で、かつ、その読み方が「○○だゆう」の場合と「○○たゆう」の場合があるので、ほとんどお手上げだ。
その幸助が五代目*玉助を襲名するというので5月文楽公演の第1部に披露口上が行われ、メインの演目である「本朝廿四孝」のうち「勘助住家の段」で横蔵(後の山本勘助)を遣った。
「本朝廿四孝」は全五段の大作で、今回はその三段目(山本勘助誕生の筋)が演じられた。
どんな話か、あらすじさえ書くこと能わず。
何しろ複雑な伏線が絡み合って、壮大な(武田信玄と上杉謙信)軍記を彷彿とさせる物語だ。
観ているときはそれなりの理解ができるのだけど、徐々に登場人物が多くなり、何某…実はナントカであった、というようなよくある話が一層話を複雑にして、とうとう消化不良のまま終わってしまった。
これは二度三度観なければ合点が行かないだろう。
襲名口上は、桐竹勘十郎、吉田簑助、吉田和生、吉田玉男、吉田蓑次郎など錚々たる布陣だった。
また、襲名狂言では人形を簑助、和生、玉男、勘十郎が、三味線を鶴澤清介、清治が、語りを呂太夫、ロ勢太夫といったベテランが参加して花を添えた。
「義経千本桜〜道行初音旅」は、歌舞伎では当たり前のように観る所作事(舞踊劇)で、これを文楽で観るのは初めてだった。
歌舞伎では(主に)長唄連中が舞台の後ろに大勢並んで踊りの伴奏をするが、文楽でも同様だった。
桜満開の吉野山を描いた背景の前に、前列に三味線が9人、後列に太夫が9人整列した様は見事だ。
人形は静御前(豊松清十郎)と狐忠信(桐竹勘十郎)だけだが、勘十郎は早変わりで忠信と狐を演ずる。
襲名披露とは直接関係のない出し物だけど、見事に美しい華やかな舞台だった。
♪2018-055/♪国立劇場-07
*幸助の父・玉幸は四代目玉助を襲名する前に亡くなったので、今回、四代目が父に追贈され、幸助が五代目を襲名した。