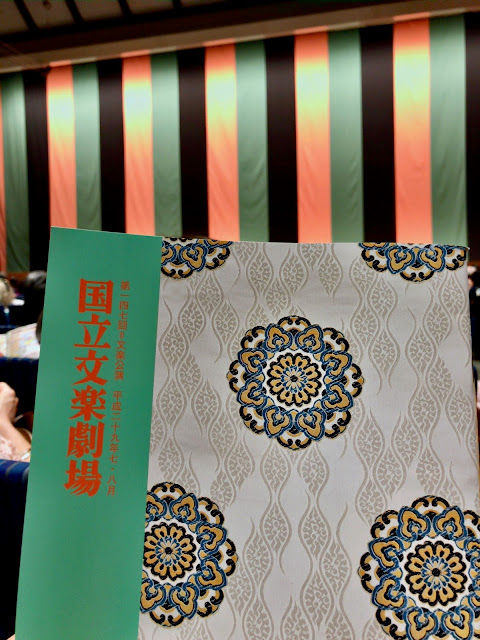2019-02-15 @国立劇場
第一部
桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)
石部宿屋の段
芳穂太夫・亘太夫/
野澤勝平・野澤錦吾
六角堂の段
希太夫・咲寿太夫・
文字栄太夫/竹澤團吾
帯屋の段
前⇒呂勢太夫/鶴澤清治
切⇒咲太夫/鶴澤燕三
道行朧の桂川
織太夫・睦太夫・小住太夫・
亘太夫・碩太夫/竹澤宗助・
鶴澤清馗・鶴澤清公・鶴澤燕二郎・
鶴澤清允
人形▶豊松清十郎・桐竹紋吉・吉田文昇・
吉田玉男・吉田勘彌・吉田勘壽・
吉田玉輝
「桂川連理柵」は「帯屋の段」が有名で、歌舞伎でもここだけ取り出したのを観ているが、今回はその前後も合わせて全4段。
話せば長い物語を端折りまくって記せば…。
帯屋の主人長右衛門(38歳)養子である。帯屋隠居の後妻のおとせ(とその連れ子儀兵衛)は、儀兵衛に店の跡を継がせようという魂胆から長右衛門に何かと辛く当たる。
一方、帯屋の丁稚長吉は隣家の信濃屋の娘お半(14歳)に夢中。お半は長吉など眼中になく、帯屋の跡取り、長右衛門を恋い慕っている。
儀兵衛はお半が長右衛門に宛てた恋文を入手したを幸いに、また、長右衛門が女房お絹の実弟のために密かに用立てた百両が店の金庫から消えていることを発見し、加えて自分たちがくすねた五十両も長右衛門の窃取だと言い長右衛門を責め立てる。
さらに、長右衛門が旅先で、長吉に言い寄られて困っているお半を我が寝所に入れた為に犯した一夜の過ちの結果、お半が妊娠してしまったことや、長吉の悪巧みでお客から預かった宝剣が見当たらなくなったことなどが重なり合い、長右衛門は八方塞がりになる。
そうこうしている間に、お半も、不義の子を宿した以上生きてはゆけないと長右衛門に書き置きを残し桂川に向かう。
もう、死を覚悟していた長右衛門だったが、お半が桂川で入水するということを知って、彼は昔の情死事件を思い起こさずにはおられなかった。
15年前に当時惚れ合った芸妓と桂川で心中しようと誓ったものの自分1人生き残ってしまった長右衛門は、これこそ天の啓示とばかり今度こそ情死を全うせんとお半の後を追うのだった。
…と長いあらすじを書いてしまった。これ以上短くすると、自分で思い出すときに役に立たないだろう。それにせっかく書いたから消さないでおこう。
実際の話はもっと入り組んでいる。
人生のほんのちょっとしたゆき違いが、運悪く重なり繋がることで、人の運命を転がし、それが雪だるまのように膨れ上がってしまうと、もう誰にも止めることはできなくなる。
現在進行形の柵(しがらみ)が、長右衛門にとってコントロール不能にまでがんじがらめに心を縛り尽くした時、ふと蘇る15年前の同じ桂川での心中未遂事件!
長右衛門にとっては、お半と桂川で心中することは、むしろ暗闇の中で見えた曙光なのかもしれない。
また、<14歳のお半>、<15年前の事件>と並べると、お半は芸妓の生まれ変わりか、あるいは芸妓が生んだ長右衛門の子供であったのかもしれない…と観客に余韻を残して幕を閉じるこの哀しい物語にはぐったりと胸を打たれる。
余談ながら、備忘録代わりに書いておこう。
人形を3人で操る場合の主遣い(おもづかい)は黒衣衣装ではなく顔を見せて演ずるのが普通だが、今回「石部宿屋の段」と「六角堂の段」では主遣いも、左遣い、足遣い同様、黒衣衣装だった(今回の公演第2部の「大経師昔暦」の「大経師内の段」も)。
不思議に思って、国立劇場に尋ねたら、極力人形に集中してもらうための演出で、昔から行われているるのだそうだ。黒頭巾をとったら弟子だった、ということはないそうだ。ま、そうでしょ。
余談その2
上方落語「どうらんの幸助」は、大阪の義太夫稽古処で「桂川連理の柵」ー「帯屋の段」のうち、後妻のおとせが長右衛門の嫁をいじめている部分を外から漏れ聞いたどうらんの幸助(喧嘩仲裁を楽しみとしている老人)が、本当の話だと勘違いして、これはほっておけないと、京都柳の馬場・押小路の帯屋に喧嘩納めにゆく、というとんでもない話でヒジョーにおかしい。
♪2019-016/♪国立劇場-03