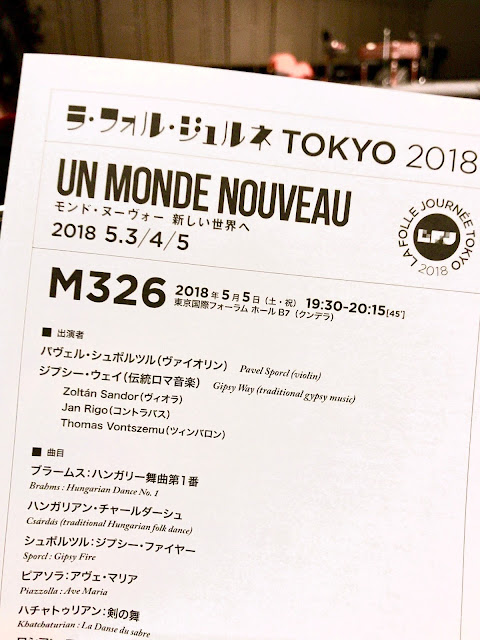2025-04-05 @東京オペラシティコンサートホール
高関健:指揮
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
大谷康子:バイオリン
ショスタコーヴィチ:バレエ組曲「ボルト」より抜粋
メンデルスゾーン:バイオリン協奏曲ホ短調 作品64
サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 作品20
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
今日の東京シティ・フィルの定期コンサートは、客演バイオリンが大谷康子。
この人も間も無く70歳。デビュー50周年。
シティ・フィルのコンマスも長くやっていた(13年間。その後東響のコンマスを21年。)。
現役のオバサマ・バイオリニストでは一番好きな人。
昨日も聴いたメン・コンを今日も聴いた。
こう言っちゃなんだけど、昨日と比べると、(オケの実力も違うんだけど)格段の差があるな。
楽器もストラディでよく鳴るし。
ツィゴイネルワイゼンも演奏した。
生でも何十回と聴いてきたが、多分、うち、彼女の演奏がこれまで一番多かったと思う。
シティ・フィルも50周年。大谷康子も50周年。
それを記念したか、メインは「春の祭典」。
なかなか強烈だった。よく鳴るホールだから打楽器の爆裂音が容赦ないよ。
でも、新国立劇場でダンス版を観たからには、オケだけではこの頃物足りない。
追記:
4/4に小笠原伸子の四大協奏曲(ベト・ブラ・メン・チャイ)を空前絶後〜などと書いたが、忘れていたっ!
今日シティ・フィルに客演した大谷康子も10年前に四大協奏曲(ビバ・メン・プロ・ブル)を弾いたのを思い出した。おまけにENCでチャールダッシュを客席を回って弾いてくれたよ!ミューザの1階席から、2CAに通ずる階段も弾きながら上り下りするのには驚いたよ。
もう、お歳を考えたらやめた方がいいね。
この時も指揮者は高関健だった。
♪2025-044/♪東京オペラシティコンサートホール-04