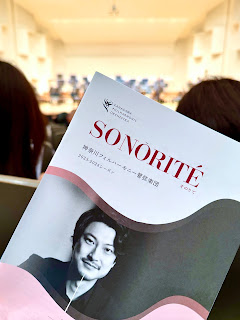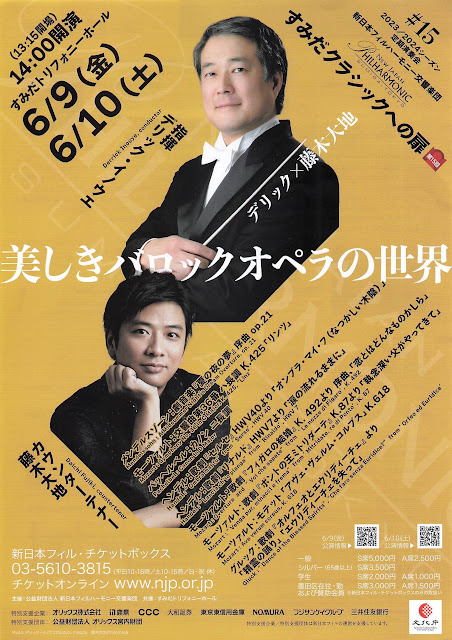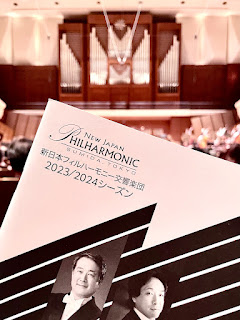2025-06-18 @みなとみらいホール
大宮臨太郎:バイオリン v
大宮理人:チェロ c
松岡あさひ:ピアノ p
------------------------------------
石田泰尚:バイオリン(特別出演)*
J.S.バッハ:<インヴェンション>から vc
クライスラー:シンコペーション vp
ファリャ(クライスラー編):スペイン舞曲 vp
サン=サーンス:く動物の謝肉祭>から白鳥 cp
メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番二短調 Op.49 vcp
------Enc--------------------
ロック(タイトル不詳)
みなとみらいホール第3代プロデューサーに就いた石田泰尚がプロデュースする弦楽合奏シリーズの1回目。といっても本人が出演するわけではない。
Pfトリオは石田組の3人だが、冒頭、シャイでおしゃべり苦手な石田があいさつとコンセプトをメモを読み上げて引き上げた。
中身は普通のピアノトリオのリサイタル。
2人ずつの組合わせで小品がまずは演奏され、メインはメン・トリだった。
大好物だが、物足りなかった。Vcがあまりにおとなしくて気分が乗らない。せめて終楽章、ガリガリ、ブリブリヤニを飛ばしてくれたら気持ちも治ったろうが、美しいだけでは良くないよ。
さて、本篇が終わって70分。既に予定は10分超過。
しかし、組長が来ているので出てこない訳にもゆくまい、と思っていたが、果たして、Encは全員上着を脱いだら、石田組のシャツだ。客席は大いに盛り上がって、何と言ったか忘れたが、ロックを演奏したが、面白くもない。
石田組は22年の5回公演を聴いて、客席の居心地が悪く世界が違うと思ったので、それ以降聴いていない。今回は、石田組ではなく、組長抜きの弦楽アンサンブルを楽しむつもりでセット券を買ったが、やはり、完売の客席は、もうおばさんばかりだし、メン・トリの1楽章の後に拍手が入るなど、まあ、和気藹々かよ。
臨太郎氏など、才能のある人だと思うけど、石田組なんかで遊んでいていいのかと心配するよ。
いやはや余計なことだけど。
♪2025-082/♪みなとみらいホール-15