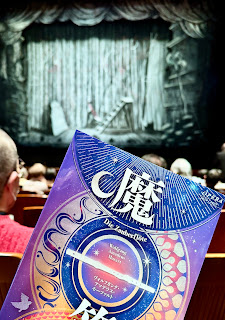2025年7月7日月曜日
オペラ「蝶々夫人」〜高校生のためのオペラ鑑賞教室
2025年6月3日火曜日
新国立劇場オペラ「セビリアの理髪師」
2025年5月21日水曜日
新国立劇場オペラ「蝶々夫人」
2025年4月12日土曜日
バレエ「ジゼル」
2025年1月3日金曜日
バレエ「くるみ割り人形」

2024年12月12日木曜日
新国立劇場オペラ「魔笛」
2024年11月28日木曜日
新国立劇場オペラ「ウィリアム・テル」 <新制作>
2024-11-28 @新国立劇場
【指揮】大野和士
【演出/美術/衣裳】ヤニス・コッコス
【アーティスティック・コラボレーター】アンヌ・ブランカール
【照明】ヴィニチオ・ケリ
【映像】エリック・デュラント
【振付】ナタリー・ヴァン・パリス
【合唱】新国立劇場合唱団
【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団
ギヨーム・テル(ウィリアム・テル)⇒ゲジム・ミシュケタ<22年椿姫>
アルノルド・メルクタール⇒ルネ・バルベラ<20年セビリアの理髪師/21年チェネレントラ/22年N響ヴェル・レク>
ヴァルテル・フュルスト⇒須藤慎吾
メルクタール⇒田中大揮
ジェミ⇒安井陽子
ジェスレル⇒妻屋秀和
ロドルフ⇒村上敏明
リュオディ⇒山本康寛
ルートルド⇒成田博之
マティルド⇒オルガ・ペレチャッコ<17年ルチア/18年N響カルミナ・ブラーナ>
エドヴィージュ⇒齊藤純子
狩人⇒佐藤勝司
ジョアキーノ・ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」<新制作>
全4幕〈フランス語上演/日本語及び英語字幕付〉
予定上演時間:約4時間35分
第Ⅰ幕
75分
--休憩30分--
第Ⅱ幕
55分
--休憩30分--
第Ⅲ・Ⅳ幕
85分
序曲は聴く機会が多いけど、オペラ本編は放映・ビデオでも観たことがない。
実際、滅多に上演されないと思う。
歌唱技術の難しさ、合唱・バレエに大勢が必要、何より長くて、正味4時間というから、2度の休憩を挟むと拘束5時間だ。ワーグナー並だよ。
そんな理由で上演されないのだろう。
でも、今回初めて観て、それだけじゃない。面白くないというのも重要な理由だろうと思った。
そういうこともあってか、新国立劇場が新制作した今回の作品も、少し端折ってあったかもしれない。
まあ、とにかく長く、話が分かりづらく、深刻な話なのだからバレエの出番などなくともいいと思うが、そこそこに用意してある。これが緊張を削ぐ。
演出家の記したものには、ロッシーに最後のオペラ作品である本作は「音楽における自殺」と評されることがあるそうだ。その正確な意味は分からないが、実際、それまでのロッシーに作品のような面白さ、分かり易さ、軽やかさがない。
どうも、失敗作ではなかったか、とど素人の僕は思うのであります。
余談ながら、日本で初めて本舞台形式で上演したのが藤沢市民オペラだそうだ。アマチュアだからこそ経費の面でもチャレンジできたのだろうな。
♪2024-163/♪新国立劇場-12
2024年10月29日火曜日
バレエ「眠れる森の美女」
2024年10月17日木曜日
東京フィル第1006回サントリー定期シリーズ
2024年10月9日水曜日
新国立劇場オペラ「夢遊病の女」