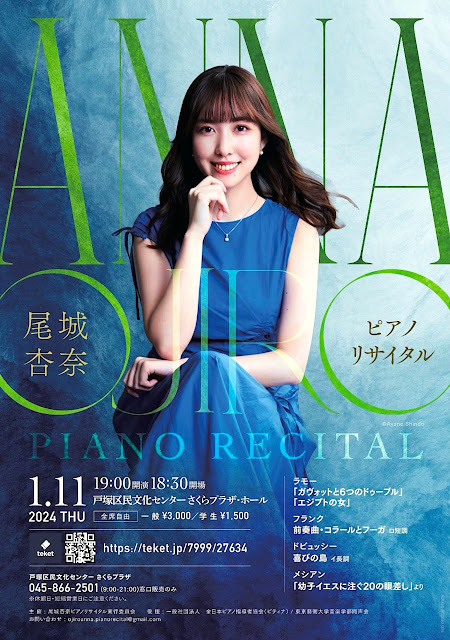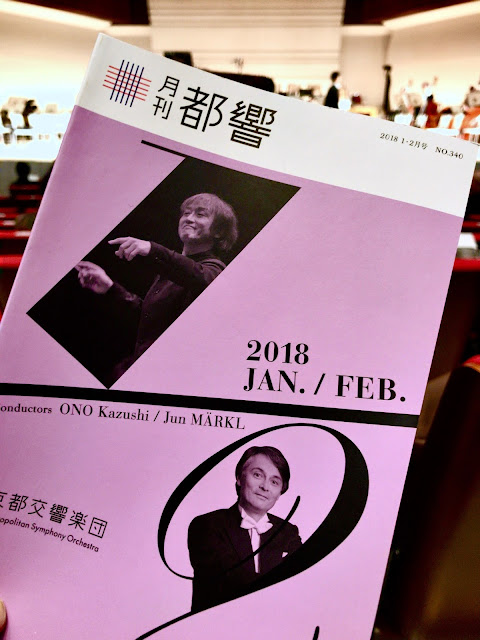2025-07-13 @みなとみらいホール
シルヴァン・カンブルラン:指揮
読売日本交響楽団
リーズ・ドゥ・ラ・サール:ピアノ*
バーンスタイン:「キャンディード」序曲
ガーシュウィン:ピアノ協奏曲ヘ長調*
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲(弦楽合奏版)
ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」
----------------------
メシアン:おお、聖なる饗宴よ*
遅刻しそうになって、客席に入るともうオケが並んでいる。自席に座る時間的ゆとりはあったが、同じ列の人に迷惑だし、ちょうど最後列の通路側が空いていたので1曲はそこで聴くことにした。みなとみらいの最後列はもちろん初めて。
このホールも23列目?以降は2階席の床下なので響きが悪かろう…と思っていたが、案外そうでもなくて間接音もよく聴こえてきたのには驚く。でも、音圧は不足だけど。
読響のプログラムは、曲の解説はあっても、その日のプログラムのコンセプトに関しては何にも書いてない。だから、今日のようなごった煮に何か共通するものがあるのかどうか分からない。
後半の2曲は、いわば耳タコだけど、前半は複数回聴いているけど多くないので、旋律の切れ端にさえ耳覚えがない。
ガーシュウィンのPf協はそこここにガーシュウィン印が刻印されていた。Pf独奏もオケとよく合わせ、キラキラ輝く音色で良かったが、Encがつまらなかったな。単に和音をボンボンと連ねているだけの作品で面白みもなく、Pfの良さも感じられない。
後半のルーマニア民俗舞曲は大好物だが、やはり原曲のPf演奏又はPfとVnくらいの編成で聴きたい。弦楽合奏では品がありすぎて民俗舞曲とは思えない。また、テンポもゆっくりすぎた。
5月に日フィルはEncで演奏したが、この時はとても「臭くて」良かったのだけど。
展覧会の絵は、読響ブラスが咆哮してヨシ!
♪2025-096/♪みなとみらいホール-020