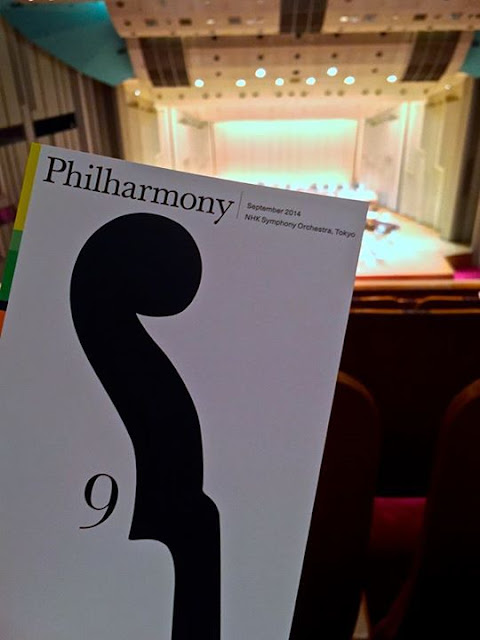2014-10-05 @県民ホール
現田茂夫:指揮
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ソプラノ:横山恵子、並河寿美、菅英三子
アルト:竹本節子、小野和歌子
テノール:水口聡
バリトン:宮本益光
バス:ジョン・ハオ
合唱:県民ホール特別合唱団、湘南市民コール、洋光台男声合唱団、小田原少年少女合唱隊
マーラー:交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」
マーラーの交響曲は、ブルックナーとともにオーケストラが取り上げる機会が多い。でも、1番(巨人)、2番(復活)、6番(悲劇的)といったところが多く、8番(千人の交響曲)はめったに舞台に上がらない(2011年のN響の演奏会は、19年ぶりだったそうだ。)。
言うまでもなく、演奏に大掛かりな人員を要するからで、僕も生で聴くのは今回が初めてだった。
昨年末から行われていた県民ホールの修復工事が終わって、リニューアルオープンのこけら落としとしてこの大曲が選ばれた。
マーラーは大好き!という訳じゃなく、むしろ若い自分は敬遠していたし今なお懐疑的だ。
でも、オーケストラの魅力という意味では外せない作曲家だし、千人の交響曲は大規模管弦楽に加えて声楽とのコラボレーションの魅力もある。
さりとて、これをテンションを維持したまま聴き通すというのは長時間を要する(約90分)ということもあり、なかなか困難で、これまで、手持ちのCDなど最初から最後までちゃんと聴いた覚えがなかった。
そこで、今回のコンサートを前にしてできるだけ時間を作ってCDやビデオディスクを聴き直した。
結論。
まず、CDで聴く音楽ではない。
CDでも、スコアと翻訳テキストを見ながらなら少しは没入度が高まるが、これも試したけど手間の割に効果は少ない。
やはり、映像付きだ。ビデオディスクを3種類*持っているので一応全部(部分飛ばしながら)視聴した。
テキストは字幕で出てくるし、長大曲の今、どこにいるのか、が分かるのはとても精神衛生に良い。
でも、問題は、(自宅では)大きな音で再生できないということだ。
そう言いながらも結構大きな音を立てているが、腹に堪えるような重低音や耳をつんざく高音は控えなくてはならないということだ。
ま、それでも、CDを聴くより何倍もの情報量があるので、楽曲理解に関してはとても効果的だった。
そんな風に、たっぷり予習をして臨んだ。
県民ホールは年が明けると設立40周年だ。多目的ホールとはいえ、アコースティックなコンサートにも対応した立派なホールでキャパシティは2500。みなとみらいホールより大きい。
耐震化などかなり大規模な修復工事だったようだが、デザイン・配色も以前のままに、じゅうたんの敷き替えや壁など塗装のやり直しですっきりときれいになった。
そのこけら落としに千人の交響曲だ。
チケットはだいぶ前に完売になったようで、満席。
千人の交響曲と名付けられているように、マーラー存命時の初演にはオケと合唱、ソリストで千人を超える大規模な演奏だったらしいが、現代、実際にはそんな大規模で演奏されることはないと思う。
野外音楽堂だとか、武道館のような施設に特設ステージを作ればひな壇に千人並ぶかもしれないが、普通のコンサートホールではそんなには載りきらない。
3種類のビデオディスクで見た限りでは、最も大規模なオーケストラ編成でも170人。それに合唱団が何人いたか分からないが、800人を超えることはないように思った。
他の2枚のディスクではさらに規模は小さい。
今回の神奈川フィルはオケが約130名、声楽ソリストが8名、合唱団が約500名で、合わせて約「650人の交響曲」と相成ったが、まあ、コンサートホールで演奏するには普通のサイズだろう。
オケも声楽もほとんど限界効用に達しているから、あと無理に帳尻合わせに人数を増やしてみても音楽効果は実質的には変わりはないと思う。
なお、オーケストラは、バンダ(舞台外別働隊)としてホーン・セクションが7本とソプラノが1人含まれている。今回は2階下手の客席に配置された。
とにかく各パートの人数が多いだけでなく使われる楽器も多彩だ。驚いたのは、シンバルが3組計6枚がジャーンと鳴らされるところが少なくとも2度はあった。ティンパニーの2組は時に見るけど、シンバルの3組は初めて観た。
≪そういえば、ビデオで観たドゥダメルの指揮でもはりシンバルは3組6枚だった。
シャルル・デュトワのNHK交響楽団もサイモン・ラトルのナショナル・ユース・オーケストラでも確かシンバルは2組4枚だった。このへんは自由に編成してもいいらしい。≫
音楽は、交響曲とはいい条マーラーは当初描いていた4楽章構成を変更して2部構成に仕立て直した。
全2楽章とも言えるし、(第1部の約30分に対し)第2部は約60分なので、これを3つに区分して3楽章、全曲では普通の交響曲のように全4楽章と解釈する見方もあるらしい。
ベートーベンの第9番のように声楽は終楽章だけに入るのではなく、しょっぱなから最後まで出ずっぱりの歌いっぱなし。
第1部は賛美歌(「賛歌」とも)「来れ、創造主なる聖霊よ」というラテン語のテキストを歌っている。
このテキストは手持ちのCD「グレゴリオ聖歌集」の中でも歌われているし、先日イングリッド・バーグマン主演の「ジャンヌ・ダーク」(48年)をビデオで観ていたら、このグレゴリオ聖歌「来れ、創造主なる聖霊よ」が流れるシーンがあった。
賛美歌については(も)詳しくないけど、この歌詞は中でも有名なもののようだ。
もっとも、マーラーが採用したのは歌詞だけでメロディは独自のものであり、グレゴリオ聖歌とは大違いの派手派手しい音楽で、全体は祝祭音楽のようである。
さて、第1部が終わると20分の休憩があった。
少なくとも予習したビデオディスク3枚の演奏では、すべて第1部の終わりに短い休止があるだけの休憩なしで演奏されているので、今回のように休憩を挟むのは珍しいのかもしれない。
第1部が終わると休憩になることが予めアナウンスされていたこともあり、その時点で拍手がパラパラ始まり、その輪が広がって大きな拍手になったけど、拍手しないで厳かに休憩に入るというのも居心地が悪いし、まあ、これで良かったのだろう。
第2部はゲーテの「ファウスト第2部」から最後の場面をテキストとしている。当然ドイツ語で歌われる。
クライマックスの歌詞はこうだ。
「乙女よ、母よ、女王よ、女神よ、ずっと慈悲深くいらしてください!」~「永遠に女性的なるものが、私達を高みへ引き上げるのだ。」
マーラーの高邁な精神性は分からない。
けど、女性の愛を神がかりの至高のものとして崇めている。
第1部は聖なる祝典曲で第2部は愛による救済といえるのかな。
本当に、本気で、マーラーがそういう精神性を追求したのかは疑問だ。
しかし、この長大曲が少しも飽きさせること無く、刺激に満ちた壮大な世界に誘ってくれるのは確かだ。
IMAX3DでSFアクション映画を観ているような体験に似ているかな。
でも、聴き終えて、ヤンヤの喝采と熱狂的なブラボーの嵐の中で、早くも僕は少しずつ覚醒していった。
興行師的才能も持ち合わせていたというマーラーの大掛かりなショーに付き合わされてような気がどうにも払拭できないでいる。
もちろん、こういう音楽があってもいい。
大管弦楽と声楽ソリスト+大合唱が奏でる大風呂敷の音楽アトラクションは楽しい。そこに言葉(テキスト)による祈りだの愛だのエロスだのとややこしいことを言い出すから、ちょっと抵抗を感ずるのだ。
でも、…いつか、素直になってマーラーの境地に近づけるだろうか?
*
サイモン・ラトルとユースオーケストラ(02年/ロイヤル・アルバート・ホール)、
シャルル・デュトワとNHK交響楽団(11年/NHKホール)、
グスターボ・ドゥダメルとベネズエラ・シモン・ボリバル交響楽団(13年/ザルツブルク祝祭大劇場)
♪2014-91/♪県民ホール-01