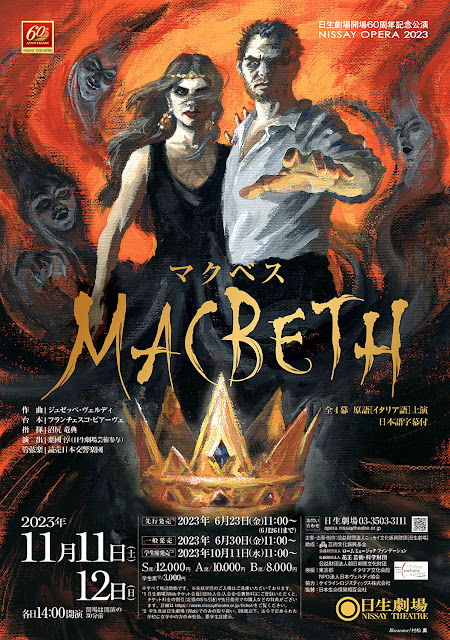2023年11月11日土曜日
2023年7月12日水曜日
オペラ「ラ・ボエーム」 〜高校生のためのオペラ鑑賞教室2023〜
2023年4月11日火曜日
新国立劇場オペラ:ヴェルディ「アイーダ」
2022年7月12日火曜日
プッチーニ「蝶々夫人」 高校生のためのオペラ鑑賞教室 2022
2021年12月25日土曜日
東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会「第九」❼
2021-12-25 @サントリーホール
角田鋼亮:指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
合唱=新国立劇場合唱団
ソプラノ:迫田美帆
アルト:中島郁子
テノール:清水徹太郎
バリトン:伊藤貴之
ベートーベン:歌劇「フィデリオ」序曲 作品72c
ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125
指揮は既に日フィルで聴いている角田鋼亮。
当然日フィルの「第九」と同じような感じだったが、日フィルに比べ少し弦が厚くなった以上に、このオケの持つ基礎的熱量が良い効果を表した。
合唱はP席で最初から待機。独唱は2楽章の後入ったが所要時間は僅か。舞台奥で待機。
声楽陣の舞台入りが流れを損なうことはなく、音楽はテンポ良く快調。
この日の午前中に聴いた都響は、音響効果の面で損をしたが、P席を合唱席に使えるサントリーでは、独唱も管楽器も舞台後方の分厚い背中の反響板がよく効いていた。
いつもの元気な東フィルが角田の軽快な指揮に乗って歌った・吠えた!
今季7回目だが、演奏時間はどの指揮者も全体的に短いのだけど、中でも今のところ一番短く63分弱。
3楽章⇒4楽章の休止はほぼゼロに等しい。
これが個人的には好きだ。
日フィルの時の指揮者とは思えぬ良い出来。
音楽と直接関係はないけど、東フィルは定期演奏会と同様、全員(出番の遅いトロンボーン奏者やパーカッションも)NoMaskで演奏する・待機する。これが良い。プロの矜持かくあるべし。
問題はあった。
日フィルの時と同じくカーテンコールの際に独唱者を舞台の前に招かなかった。
ソプラノ大賞!候補の迫田ちゃんも、舞台前に出してもらえない。
角田氏曰く「オケのルールなので自分も残念だった」と仰る。他の5オケはすべて舞台前での拍手に応えた。
東フィルは奏者がNoMaskで頑張っているのに納得できん!
2021年11月16日火曜日
DOTオペラ:ヴェルディ:歌劇「アイーダ」
2021-11-16 @ミューザ川崎シンフォニーホール
指揮:佐藤光
演出:山口将太朗
照明:稲葉直人
舞台監督:伊藤桂一朗
合唱指揮:辻博之
管弦楽:アイーダ凱旋オーケストラ
合唱:Coro trionfo
アイーダ:百々あずさ
ラダメス:村上敏明
アムネリス:鳥木弥生
アモナズロ:高橋洋介
ランフィス:伊藤貴之
エジプト国王:松中哲平
伝令:所谷直生
巫女:やまもとかよ
ダンサー5人
ヴェルディ:歌劇「アイーダ」
(全4幕、セミ・ステージ形式・オーケストラ小編成版、字幕付き)
演奏会形式オペラ。が、大いに凝った作りだ。
まずは「アイーダ凱旋オーケストラ」って名前に惹かれたよ。遊び心十分。実際は、いろんなプロオケメンバーによる一夜限りのオケ。弦19人、打・鍵3人にアイーダ・トランペット4人という小編成だが、全く不足を感じさせない。
合唱は東響コーラスの有志94人!この数を、一昨日同じ場所で聴いた「カルミナ・ブラーナ」でも欲しかったね。
合唱団は舞台周りのP席とバルコニー4ブロックにゆとりを持って並んだ(そもそも、今日の客席は1C-2CAB-3Cだけで4階と周囲のバルコニーはお客を入れていなかった。)。
P席が塞がっているので、歌手の演唱はステージの奥、客席側前方、上手・下手に、時にはバルコニーと縦横無尽。アイーダ・トランペットも2階左右バルコニーに陣取って超ステレオ効果!
演奏会形式と言っても、サントリーの「ホールオペラ®︎」に近い。
衣装、小道具、照明で雰囲気を盛り上げてくれる。
さて、歌手は、百々(どど)あずさ、村上敏明、鳥木弥生、伊藤貴之ら名の知れたベテラン・中堅。
よく響くミューザでは声もよくとおりホンに人間の声の美しさに酔った。特に鳥木ちゃんのアムネリスがけっこうしおらしくて、本作に限っては「アイーダ」というより「アムネリス」というタイトルがふさわしかったよ。
演奏会形式でも手抜きなしで、グランドオペラらしくバレエもちゃんと5人登場して踊ってくれたのも嬉しい。
この贅沢な時空を享受して僅かにS席5千円って大丈夫なのかと心配したよ。
こりゃ少しカンパして帰るかと真面目に思ったが、よく考えたら財布を持たないので現金は1円も持っていなかった。
国のコロナ対策の一環の助成事業ならこそ実現できたのかも。
平日の17:30開演は勤め人には厳しいが、もう少し熱心に宣伝をしていたら、もっとお客が入ったのではないか。カーテンコールは熱く、長かったが、なにしろお客の絶対数が少ないので一生懸命の拍手も嵐のような轟音には至らなかったのが残念。
500〜600人の入りだったそうだ。
因みに、「DOTオペラ」とは、主唱者の百々(DODO)あずさ、小埜寺(ONODERA)美樹<コレペティトゥールであり今回のピアニスト>、鳥木(TORIKI)弥生の頭文字を綴ったもの。
2021年9月12日日曜日
ベッリーニ作曲「清教徒」全3幕 藤原歌劇団公演(共催:新国立劇場・東京二期会)新制作
2019年12月14日土曜日
名曲全集第152回 年末恒例「歓喜の歌」<第九②>
秋山和慶 :指揮
東京交響楽団
合唱:東響コーラス
バイオリン:シャノン・リー(第7回仙台国際音楽コンクール2位(最高位))
ソプラノ:吉田珠代
メゾソプラノ:中島郁子
テノール:宮里直樹
バリトン:伊藤貴之
ブルッフ:バイオリン協奏曲第1番ト短調 作品26
ベートーベン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125
-------------
蛍の光
愈々本格的に第九の始動開始。既にアマオケで1回聴いているがプロでは1番バッター。伝統の秋山・東響「第九」だ。
40年以上続いた秋山「四季と第九」は今年からノットが「第九」を振ることになって一応幕を閉じた。
横槍を入れたテイのノットは独唱陣を別キャストで「第九」をやるが、ホームであるミューザではやらない!のが面白くない。
一方、秋山翁も強かなもので「四季と第九」はやめるが、「バイオリン協奏曲と第九」は続ける様で同慶の至りだ。
「四季」といっても実際は「二季」だったので、今日の様に1曲丸ごと聴ける方がいい。新人起用も踏襲して秋山第九健在!
最後の「蛍の光」もペンライトからLEDに替わったが、この古色蒼然たる演出も続くことで価値が出てくる。
演奏は、いつもやや遅めで安定感がある。
東響も40年からやっているので、メンバーの多くは身体に染み込んでいるのだろう。
とにかく、安心の「第九」である。
秋山翁には末長く続けてほしい。
♪2019-205/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-29
2019年9月5日木曜日
藤原歌劇団公演オペラ「ランスへの旅」
折江忠道:総監督
園田隆一郎:指揮
松本重孝:演出
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
合唱:藤原歌劇団合唱部/新国立劇場合唱団/二期会合唱団
コリンナ:ローマの女流詩人⇒砂川涼子
メリベーア侯爵夫人:ポーランドの寡婦⇒中島郁子
フォルヴィル伯爵夫人:若い寡婦⇒佐藤美枝子
コルテーゼ夫人:金の百合亭主人⇒山口佳子
騎士ベルフィオール:仏士官。コリンナに愛⇒中井亮一
リーベンスコフ伯爵:ロシア将軍⇒小堀勇介
シドニー卿:英軍人。コリンナに愛⇒伊藤貴之
ドン・プロフォンド:文学者⇒久保田真澄
トロムボノク男爵:独陸軍少佐⇒谷友博
ドン・アルバーロ:スペインの提督⇒須藤慎吾
ドン・プルデンツィオ:医者⇒三浦克次
ドン・ルイジーノ:フォ〜夫人のいとこ⇒井出司
デリア:ギリシャ孤児。コリンナ下女⇒楠野麻衣
マッダレーナ:女中頭⇒牧野真由美
モデスティーナ:フォ〜夫人の小間使い⇒丸尾有香
ゼフィリーノ:使者⇒山内政幸
アントニオ:給仕長⇒岡野守
ほか
ロッシーニ:歌劇「ランスへの旅」
オペラ全1幕〈字幕付きイタリア語上演〉
予定上演時間:約3時間
第Ⅰ部105分
--休憩20分--
第Ⅱ部55分
藤原歌劇団公演に二期会・新国も参加した大掛かりなプロダクション。
独唱者17人に合唱がついて目まぐるしく賑やか。
幸い同じ藤原歌劇団の同じ演出による2015年の日生劇場版を観ていたので筋書きは覚えているが、初めての人には特段の説明もなく話が進むので置いてきぼりにされるかもしれない。
ま、それでも構わぬ歌こそ命の歌劇だ。
1825年パリ近郊の湯治場、と言っても高級ホテル。
フランス王シャルルのランスでの戴冠式見物の為に同じ宿に集った紳士淑女たち。そこであれやこれやのプチ・ドラマが繰り広げられる。目的のランス行きが不可能となるもパリでもお披露目が行われると聞き安堵して、とりあえずランスへの旅の費用として集めたお金で大宴会を開くことになった。
ここまでも一言もセリフはなく、レシタティーヴォとアリアの連発だ。ともかく、次から次と歌に次ぐ歌。
クライマックスの大宴会で紳士淑女は出身国にちなむ歌を交代で披露する。実は、集まった紳士淑女たちはそれぞれ異なる国の出身者なのだ。この辺が巧い設定だ。
ドイツ人の男爵はドイツ賛歌、
ポーランドの公爵夫人はポロネーズ、
ロシアの伯爵はロシア賛歌、
スペインの海軍提督はスペインのカンツォーネ、
イギリス軍人は英国国歌、
フランスの伯爵夫人と騎士は二重唱でブルボン王家賛歌、
ティロル出身の夫人はヨーデル颯民謡
を歌い継ぎ、シメに即興詩人が全員の投票によって決まったお題を基に即興で「シャルル王」賛歌を歌い、最後は全員で「シャルル王」賛歌を歌って華やかに幕。
主要な17人の歌手の中には何度も聴いている人もいるが初めて聞く名前もあった。だが、みんな巧いことにいつもながら驚く。よく通る声で、ベルカントの難しそうな細かく早い装飾をコロコロ歌う。
独唱から二重唱、六重唱、果ては14人、17人の強力な合唱も実に聴き応えがあった。
中でも一番は主役格の砂川涼子。
この人はホンに何度も聴いているけど、今日はその実力を思い知らされた感がある。今年はまだ日生劇場の「トスカ」、紀尾井ホールでのリサイタルを追っかけなくちゃ!
2018年11月27日火曜日
新国立劇場オペラ「カルメン」
指揮:ジャン=リュック・タンゴー
演出:鵜山仁
美術:島次郎
衣裳:緒方規矩子
照明:沢田祐二
振付:石井 潤
合唱⇒新国立劇場合唱団
管弦楽⇒東京フィルハーモニー交響楽団
カルメン⇒ジンジャー・コスタ=ジャクソン
ドン・ホセ⇒オレグ・ドルゴフ
エスカミーリョ⇒ティモシー・レナー
ミカエラ⇒砂川涼子
スニガ⇒伊藤貴之
モラレス⇒吉川健一
ダンカイロ⇒成田眞
レメンダード⇒今尾滋
フラスキータ⇒日比野幸
メルセデス⇒中島郁子
ビゼー:「カルメン」全3幕〈フランス語上演/字幕付〉
予定上演時間:約3時間35分
第Ⅰ幕55分
--休憩25分--
第Ⅱ幕45分
--休憩25分--
第Ⅲ幕65分
17年1月公演と同演出だが主要キャストはミカエラ(砂川涼子♡)以外は総変わり。
が、カルメン役もエスカミーリョ役も、それぞれの役が得意の声域ではないように思えた。低域が中高域に比べてすっきりと出ていない、地声風の箇所があった。
それに何より残念なのはカルメンに華やかさや妖しさが不足していた点だ。でも、これは、前回との比較でそう思ってしまうのであって、今回を初めて観た人には満足できたのかもしれない。
 美術・衣装とも前回と同じだったが、第1幕のタバコ工場の女工たちが大勢登場するシーンの彼女達の衣装の色彩設計の妙に、今回は感心した。
美術・衣装とも前回と同じだったが、第1幕のタバコ工場の女工たちが大勢登場するシーンの彼女達の衣装の色彩設計の妙に、今回は感心した。4、50人居たろうか、その大勢の衣装の色合いが実に美しい。原色といえば白と黒だけ、それも極めて少ない。他の色合いはベージュを基調にした〜といってもカラフルではある〜とはいってもすべてパステルカラーの穏やかさ、渋さがある。
この色彩設計が衣装担当によってもたらされたのか、美術担当の仕事なのか分からないが見事で、このシーンは一幅の名画のようでもあった。これもオペラ観劇の楽しみの一つだなと得心した。もっとも前回はほかの事に気を奪われて衣装の色彩には気がつかなかったが。
いずれにせよ、次々と繰り出されるお馴染みの名曲・名旋律。
「カルメン」は頭から尻尾まで餡が詰まった鯛焼きの如し。
2018年6月17日日曜日
日生劇場会場55周年記念公演 NISSAY OPERA 2018 モーツァルトシリーズ『魔笛』
指揮:沼尻竜典
演出:佐藤美晴
管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団
合唱:C.ヴィレッジ・シンガーズ
ザラストロ:伊藤貴之
タミーノ:山本康寛
パミーナ:砂川涼子
夜の女王:角田祐子
パパゲーノ:青山貴
パパゲーナ:今野沙知恵
モノスタトス:小堀勇介
ほか
モーツァルト作曲 オペラ『魔笛』全2幕
(ドイツ語歌唱・日本語台詞・日本語字幕付)
予定上演時間:約3時間
第Ⅰ幕 70分
--休憩20分--
第Ⅱ幕 90分
日生オペラは制約(料金が安いから制作費なども多くは取れない。また、詳しいことは知らないけど舞台機構も大型のせりや回り舞台は無いのではないか。)の大きい中で舞台や衣装等も工夫が凝らされているのにいつも感心する。
今日の魔笛も、主要な舞台装置は中央に一つきり。それがくるくる回転して、照明を受けて、いろんなシーンを形作る。
役者の衣装もあまり豪華とは言えない。パパゲーナの靴などもっといいのを履かせてあげたいと思ったよ。
それでも、いつも概ね楽しめる舞台を作り上げるのは大したものだ。
今日も楽しんだが、なんと言っても一番良かったのはパミーナ役の砂川涼子。役のせいもあるけど「祭りの準備」の頃の竹下景子そっくりでカワユイ!もちろん歌も素晴らしい。
今回、砂川涼子のほかには伊藤貴之(ザラストロ)、青山貴(パパゲーノ)くらいしか覚えのある歌手は見当たらなかったが、若干の不満はあったものの、みんな上手にこなしていたと思う。
ところで、オペラ一番人気とも言われる「魔笛」だが、ストーリーは難しいというか、ザラストロや夜の女王の本質は何か、まあ、よく分からない。専門家がいろんな解釈を提供しているが、今回の演出でもよく分からなかった。
この作品(だけではなく、物語として首を傾げるものは少なくない。)は、もう、おもちゃ箱をひっくり返したような、次々登場する耳慣れた、それゆえ心地良い音楽の砲列を楽しむのが一番かな、と思っているけど、どうか。
新国立劇場では来シーズンの幕開けが「魔笛」だ。これを楽しみにしている。
♪2018-072/♪日生劇場-01
2017年7月1日土曜日
NISSAY OPERA 2017 ベッリーニ『ノルマ』
指揮:フランチェスコ・ランツィッロッタ
演出:粟國淳
ノルマ⇒マリエッラ・デヴィーア
アダルジーザ⇒ラウラ・ポルヴェレッリ
ポリオーネ⇒笛田博昭
オロヴェーゾ⇒伊藤貴之
クロティルデ⇒牧野真由美
フラーヴィオ⇒及川尚志
東京フィルハーモニー交響楽団
藤原歌劇団合唱部/びわ湖ホール声楽アンサンブル
ベッリーニ:オペラ「ノルマ」全2幕〈字幕付き原語上演〉
「ノルマ」は、「オテロ・タイス・トスカ・マノン・ルチア(正確には”ランメルモールのルチア”)」と並んで<3文字オペラ>の代表格。…とは誰も言ったりしていないが、タイトルがカタカナ3文字のオペラは成功率が高いみたいだ。
「ノルマ」も今回舞台では初聴きだが、このオペラは結構有名だから、目にし、耳にする機会が多いので、ノルマが歌う有名なアリア「浄き女神」(Casta Diva)は単独で聴いたこともある。
実に美しいこの曲は歌うには大変難しいそうで、得意にしていたマリア・カラスでさえ、あらゆるアリアの中で一番難しいと言ったとか。
今回のノルマ役のマリエッラ・デヴィーアと言う人は、やはりソプラノの難曲「ルチア」の主役で一世を風靡した歌手だそうだが、ルチア役を10年ほど前に引退し、最近、60歳代になってカラスが難曲と言った「ノルマ」を歌い始めたそうだ。
ところで、耳に馴染んだアリアといえば、この「浄き女神」だけで、あとはひとかけらも思い出せる音楽はなかった。しかし、全編分かりやすい音楽だ。ドラマの方は酷い話があったものだと思うような悲劇だが、その割に音楽の方で悲劇性は強調されていないのがやや物足りなかった…というのが初聴きの印象。
♪2017-112/♪日生劇場-02
https://youtu.be/D9Mylq8rZz8
2017年4月19日水曜日
オペラ:ヴェルディ「オテロ」
オペラ:ジュゼッペ・ヴェルディ「オテロ」全4幕〈イタリア語上演/字幕付〉
演出:マリオ・マルトーネ
 美術:マルゲリータ・パッリ
美術:マルゲリータ・パッリ衣裳:ウルスラ・パーツァック
照明:川口雅弘
再演演出:菊池裕美子
舞台監督:大澤裕
オテロ⇒カルロ・ヴェントレ
デズデーモナ⇒セレーナ・ファルノッキア
イアーゴ⇒ウラディーミル・ストヤノフ
ロドヴィーコ⇒妻屋秀和
カッシオ⇒与儀巧
エミーリア⇒清水華澄
ロデリーゴ⇒村上敏明
モンターノ⇒伊藤貴之
伝令⇒タン・ジュンボ
序曲無し。
 いきなり激しく劇的な大音響の音楽と共に幕が上がるとベネチアの港町。
いきなり激しく劇的な大音響の音楽と共に幕が上がるとベネチアの港町。実際の水を使った運河を含めこの大掛かりな舞台装置は全4幕ほぼ不変。代わりに照明が気分を変える。
大編成の東フィルが迫力の演奏だ。歌手も負けず声量豊か。
今回は2階最前列のど真ん中という最良席。
醜悪が無垢を打ち砕く救いの無い物語に圧倒されるも至福の2時間45分。
♪2017-061/♪新国立劇場-3