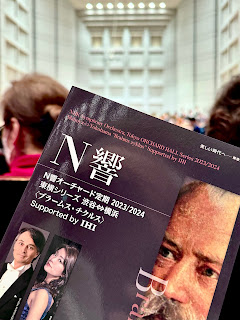2018-02-22 @東京文化会館
台本・作曲:リヒャルト・ワーグナー
歌劇「ローエングリーン」全3幕
日本語字幕付き原語(ドイツ語)上演
準・メルクル:指揮
深作健太:演出
合唱:二期会合唱団
管弦楽:東京都交響楽団
装置:松井るみ
衣裳:前田文子
照明:喜多村 貴
合唱指揮:増田宏昭
演出助手:太田麻衣子
舞台監督:八木清市
公演監督:大野徹也
公演監督補:牧川修一
ハインリヒ・デア・フォーグラー⇒金子宏
ローエングリン⇒小原啓楼
エルザ・フォン・ブラバント⇒木下美穂子
フリードリヒ・フォン・テルラムント⇒小森輝彦
オルトルート⇒清水華澄
王の伝令⇒加賀清孝
4人のブラバントの貴族⇒菅野敦、櫻井淳、湯澤直幹、金子慧一
コンサート等で忙しくてナマのオペラを観る機会はあまり多くないけど、METのライブビューイング始めBSプレミアムなどで放送される(た)オペラは、よほど現代の、作曲家の名前も聞いたことがないような作品は別にして、大抵録画し、今では録画済みディスクも相当な枚数になっている。
それらは放送時点で観たり、暇を見つけて後日観たり、ナマオペラ鑑賞の前の予習のために観たりして結構鑑賞本数も多い。それにつけても思うのは、オペラの場合はその成否を決するのは一に「演出」にあるように思う。
11月末に日生劇場で観た「こうもり」と2ヵ月後に新国立劇場でみた「こうもり」は面白さという意味では全然レベルが違った。これは舞台美術や歌手の技術に差もあったろうが、何と言っても後者の演出が良かったからだ。

今回の「ローエングリーン」は、どんな物語になったか。
もうスタートから頭が混乱する。
原作台本には登場しないはずのルートヴィヒⅡが第1幕前奏曲からうろついており、同時に子供時代のルートヴィヒⅡも声は発しないが同じ時空に存在し、ルーロヴィヒⅡの方はそのうちローエングリーンに化身する。かと思うと若いローエングリーンも登場し、こちらはエルザの見た夢なのか象徴としての存在なのか、一言も発しない。
本来は、単純なメルヘンであるはずなのに、複雑怪奇な物語にしてしまって、もう訳が分からない。
今回の演出は深作健太だ。こういう他ジャンルから演出家を招くとつい力が入り、”独自色”を出したがって、本来のワーグナーが書いた歌劇からは遠ざかってしまう。本物のルートヴィヒⅡが夢中になった「ローエングリーン」とは似て非なるものになる。
このように大胆に翻案するのを「読み替え演出」というらしいが、やり過ぎは禁物だ。自己満足はできるが観客は置いてきぼりになってしまう。
「ローエングリーン」の過去の演出では2011年のバイロイト音楽祭の”ねずみの兵隊・貴族たち”という奇抜な演出が賛否を引き起こしたという。ちょうどそのをディスクで持っているが、これなど笑止千万だ。
それで、今回の深作演出にはまったく乗れなかった。なぜこの役がここで登場するのかなどの意味を考えていたらちっとも楽しめなかった。
しかし、舞台美術は良かった。かなりお金を掛けている感じだ。
また、声楽独唱陣も合唱団も、都響の演奏もすべてに満足できた。とくに主要独唱者などみんなよく通る声で声量がある。こんなに上手ならなにも外国から歌手を招かなくとも日本人だけでやれるのではないか、と思ったくらいだ。
♪2018-023/♪東京文化会館-02