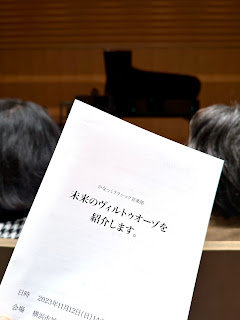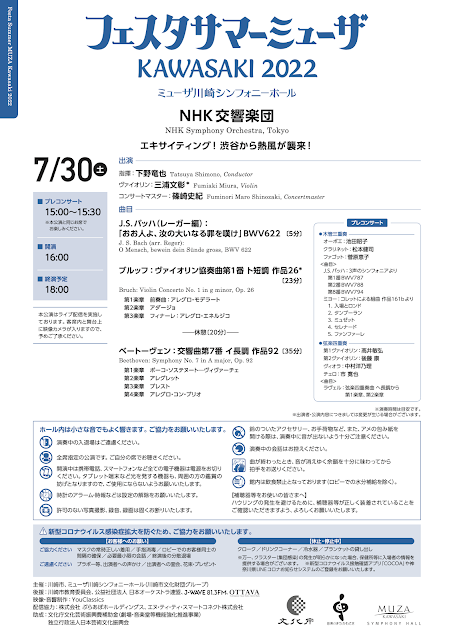2015-05-10 @ミューザ川崎シンフォニーホール
高関健:指揮
大谷康子:バイオリン
東京交響楽団
ビバルディ:バイオリン協奏曲 イ短調 RV356 作品3-6
メンデルスゾーン:バイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
プロコフィエフ:バイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
ブルッフ:バイオリン協奏曲 第1番
------------
アンコール(大谷康子)
モンティ:チャールダッシュ(管弦楽伴奏付き)
今回は、東響のソロ・コンサートマスターである大谷康子がバイオリン協奏曲を1人で4曲演奏するというので、新聞などにも取り上げられて話題の演奏会だった。
4曲と言っても、ビバルディの作品は3楽章合わせても約5分という小品だが、残るメンデルスゾーン、プロコフィエフ、ブルッフだけでもかなりのボリュームだ。
これらを完全暗譜で、ノーミス(だと思うよ。)で弾き切ったのは並みのプレイヤーじゃないね。
今年デビュー40周年というから、藝大在学中がデビューと数えても還暦は過ぎているはずだ。
それがそうは見えない童顔は、ホンに昔からヘアースタイルとともにちっとも変わっていないように思う。
若い頃はチョッと冷たさも感じたけど、最近は人格も円熟しているんだろうな、いつも穏やかでニコニコしている場面が多い。
オケもうまい。東響はなんというのか、非常によくまとまっているような気がするな。特に管楽器はまったくミスをしたのを聴いた覚えがない。
今日は、御大コンマスのバックに徹して、気脈を通じたアンサンブルを繰り広げてくれた。
指揮の高関マエストロも人格温厚そうで、本当に東響のホームグラウンドであるミューザでアト・ホームなコンサートであった。
4曲も弾いたので、まさか、アンコールはあるまいと思っていたけど、いつまでも続く歓呼を制して愛器ストライディバリウス("Engleman")を構えると同時に高関マエストロも指揮台にひょいと飛び乗って、チャールダッシュが始まった。
それだけでもびっくりだったが、何と、途中から、正にロマ(チャルダーシュはロマの音楽だ。)の音楽の演奏形態を再現するかのように、バイオリンを弾きながら1階客席の、先ずは下手に降りて最後尾まで(といってもミューザの1階は11列しかないが)行き、さらに最前列に戻って今度は上手を最後尾まで登り、もう、戻ってくるだろうと思ったら、なななんと演奏しながら階段を上がって2階席まで上がったのにはびっくりというより心配になった。
ミューザの客席構造はまことに変わっていて、全体がうずを巻いた階段状になっているので、床が水平な場所といえば1階席(ここも階段状だが)位のもので、ほかは床が傾いているのだ(もちろん、椅子は水平だけど。)。だから、僕は客席内を歩くときはいつも足元に注意をしている。傾いた床を結ぶ階段てコワイのだ。
そんな訳で、バイオリンを弾きながら客席を回ってくれるというのは近くに座っているお客にはサプライズ・プレゼントだけど、僕は少しハラハラした。早く舞台に戻ったほうがいいよ!と心の中で呼びかけていたのだけど。
ま、無事に楽しい曲が終わり、さらにやんやの喝采を受けて華々しい大谷康子ショーが幕を下ろした。
久しぶりにミューザは熱気に満ちた。
♪2015-47/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-08