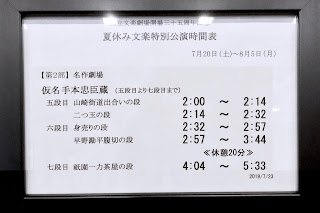2016-12-02 @国立劇場
竹田出雲・三好松洛・並木千柳=作
通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら) 第三部 四幕八場
国立劇場美術係=美術
八段目 道行旅路の嫁入
九段目 山科閑居の場
十段目 天川屋義平内の場
十一段目 高家表門討入りの場
同 広間の場
同 奥庭泉水の場
同 柴部屋本懐焼香の場
花水橋引揚げの場
(主な配役)
【八段目】
本蔵妻戸無瀬⇒中村魁春
娘小浪⇒中村児太郎
【九段目】
加古川本蔵⇒松本幸四郎
妻戸無瀬⇒中村魁春
娘小浪⇒中村児太郎
一力女房お品⇒中村歌女之丞
由良之助妻お石⇒市川笑也
大星力弥⇒中村錦之助
大星由良之助⇒中村梅玉
【十段目】
天川屋義平⇒中村歌六
女房お園⇒市川高麗蔵
大鷲文吾⇒中村松江
竹森喜多八⇒坂東亀寿
千崎弥五郎⇒中村種之助
矢間重太郎⇒中村隼人
丁稚伊吾⇒澤村宗之助
医者太田了竹⇒松本錦吾
大星由良之助⇒中村梅玉
【十一段目】
大星由良之助⇒中村梅玉
大星力弥⇒中村米吉
寺岡平右衛門⇒中村錦之助
大鷲文吾⇒中村松江
竹森喜多八⇒坂東亀寿
千崎弥五郎⇒中村種之助
矢間重太郎⇒中村隼人
赤垣源蔵⇒市川男寅
茶道春斎⇒中村玉太郎
矢間喜兵衛⇒中村寿治郎
織部弥次兵衛⇒嵐橘三郎
織部安兵衛⇒澤村宗之助
高師泰⇒市川男女蔵
和久半太夫⇒片岡亀蔵
原郷右衛門⇒市川團蔵
小林平八郎⇒尾上松緑
桃井若狭之助⇒市川左團次
ほか
長大な芝居が遂に終わってしまった。
ま、今月中にもう一度観ることにしているけど、この先、<全段完全通し>は生きているうちには観られないだろうから良い経験ができた。
この芝居に関しては、第2部から(第1部も遡って)初めて台本を購入した。もちろん第3部も購入したので、今日は第3部の1回目でもあるので、台本と照らし合わせながら舞台を観たので非常に良く分かった。しかし、月内の次回鑑賞時は一切の解説本無しで舞台に集中しようと思う。
八段目道行は舞踊劇(竹本の伴奏による。セリフはない。)だが、加古川本蔵の妻(戸無瀬=魁春)と娘(小浪=児太郎)の東海道を京都山科にいる小浪の許嫁である力弥の屋敷までの嫁入りの旅で、不安な要素もないではないが全段中一番平和な話だ。
背景の景色が変化することで2人の道中が運んでゆくのが分かるようになっていて、他家の嫁入り行列なども紙人形で作ってあってユーモラスでもある。
九段目山科閑居の場では加古川本蔵の一家の物語が胸を熱くする。本蔵の幸四郎、由良之助の梅玉は芝居のタイプが全然違うけど、そんなことにはお構いなしが歌舞伎の面白さでもある。
由良之助の妻お石を演じた市川笑也という役者のことは全然知らなかった。多分、これまで一度も芝居を観たことがなかったのではないか。しかし、冷徹で筋目を通そうとする武士の妻お石を実に好演したと思う。厳しいばかりではなく、情の人でもあるところをさり気なく見せるところが良かった。今後楽しみな役者だ。
小浪は一部で米吉が演じて実に可愛らしかったので今回も力弥より小浪を演じたら良かったが、しかし、今回の児太郎の小浪も実に良かった。この人の芝居を始めていいと思ったよ。
講談・浪曲では「天野屋利兵衛は男でござる。」で知られる天川屋義平の十段目は筋に無理があるが、ここにも義理と人情の板挟みで苦しむ町人の物語が殺伐とした仇討ち物語に良い味付けではある。
いよいよ十一段目。
幕が開くと広い舞台に拵えられた高家の表門。その前に所狭しと46人の赤穂義士が居並ぶ様にまずは圧倒される。
こんなに大勢の役者が揃って同じ場面に立つという芝居がほかにあるだろうか。
このあとの討ち入りの様は、いわゆる歌舞伎風の踊りのような立ち回りではなく、時代劇映画の殺陣を観るようなかなりリアルな厳しいものなので驚いた。
ようやく師直の首を打ち取り、判官の位牌の前に供えた由良之助は、まずは師直に一矢を報いた矢間(やざま)重太郎(中村隼人)に手柄として最初の焼香を命ずる。次に足軽でありながらその忠義心から義士の連判状に名を連ねてもらった寺岡平右衛門(錦之助)に対し、勘平の遺した財布を手渡して妹婿の代わりに焼香させる。もう、ここでかなり目頭が熱くなる。
その後亡君の菩提寺まで引き揚げる途中の花水橋でそもそもこの事件の発端を作った若狭之助(左団次)に呼び止められ、あっぱれの本懐を讃えられ、義士の姓名を我が胸に刻みたいという申し出に応じて由良之助以下46人(これに勘平を加えて47士)が高らかに、誇らしげに名乗りを上げ、花道に消えてゆく。
芝居興行の世界では「忠臣蔵にはずれ無し」と言うそうだが、300年にわたって庶民に愛されてきたのもなるほ納得。いやはや面白い芝居をたっぷりと観せてもらった。
♪2016-166/♪国立劇場-09