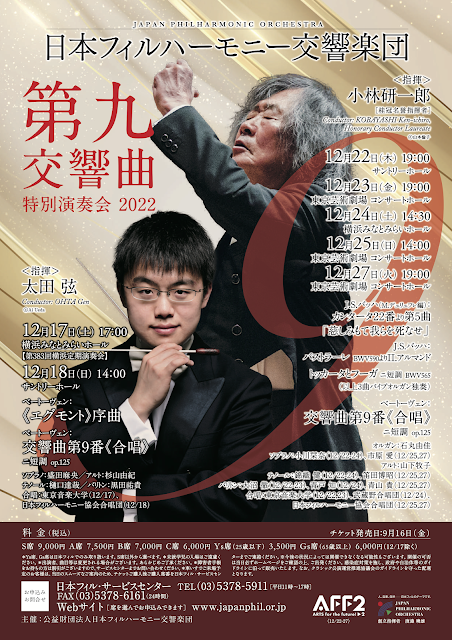2019-07-10 @新国立劇場
プッチーニ:オペラ「蝶々夫人」
〜高校生のためのオペラ鑑賞教室
全2幕〈イタリア語上演/日本語字幕付〉
予定上演時間:約2時間35分
第Ⅰ幕50分
--休憩25分--
第Ⅱ幕80分
 飯森範親:指揮
栗山民也:演出
島次郎:美術
前田文子:衣裳
勝柴次朗:照明
飯森範親:指揮
栗山民也:演出
島次郎:美術
前田文子:衣裳
勝柴次朗:照明
蝶々夫人⇒木下美穂子
ピンカートン⇒樋口達哉
シャープレス⇒成田博之
スズキ⇒小林由佳
ゴロー⇒晴雅彦
ボンゾ⇒峰茂樹
ヤマドリ⇒吉川健一
神官⇒山下友輔
ケート⇒山下千夏
高校生のためのオペラ鑑賞教室だった。あいにくと僕は高校生ではないので!前売り指定券は買えない。
公演日の前日の16時に翌日売り出される「当日券」の発売予定枚数がNET上に発表され、当日の10時以降に新国立劇場ボックスオフィス(B.O.)で電話で予約し窓口で引き換える(直接窓口に行って購入することもできる。)という仕組みだ。

今回は6日から12日までの7日間で6公演あり、ダブルキャストで交代に出演する。
そして、僕は蝶々夫人役で言えば木下美穂子(別の組は小林厚子)の組の公演を是非とも聴きたかった。
それで、毎日、木下組公演の前日の、翌日前売り券発表状況を見ていたが、初日(8日)がわずか10枚で、これではたとえ買えてもろくな席はあるまいと断念。
次の出番(10日)の当日券は20枚と倍増したが、ここが思案のしどころ。チャンスはもう一回あるのだけど、その日が5枚とかになったらもっと厳しいことになる。
で、その20枚に賭けた。
当日、10時から新国立劇場のB.O.に電話(固定と携帯電話2台)をかけるのだけど、もう、ハナから話し中で繋がらない。
20分以上かけ続けて、ようやく繋がってた。
チケットはまだ残っていた。
残りものに福あり。
信じられないことに1階のセンターブロックが残っていた。
あいにく最後列の1列前だった。
もし自分で選んで買うなら、避けるような席だけど、舞台から遠いといっても21列目。普通に買えば安価な公演であれS席だから2万円はする。これがなんと4,320円とは信じられない価格。ありがたや。
購入の手続きを済ませて、あまり時間もなく家を出た。
「高校生のためのオペラ鑑賞教室」である。オペラパレスは高校生ばかり。それもどういう訳か圧倒的に女学生が多い。なんと賑やかで晴れやかなこと。
「鑑賞教室」と言い条スタッフ・キャストは6月の通常の公演とほとんど変わらない。演出も同じだから、舞台装置も美術も衣装も同じ。指揮者は変わったが、一流の指揮者であることには変わりはない。
主要な歌手は変わったが、一部は6月公演と同じだ。
肝心要の蝶々夫人は木下美穂子。彼女は、文句なしの一流で、2006年の(随分古いが)東京文化会館の二期会公演で彼女の蝶々夫人を聴いている。最近では読響との「第九」や文化会館での「ローエングリーン」など。
2001年に日本三大声楽コンクールを1年で制覇したという伝説のツワモノで、今回は是非、木下美穂子でなくちゃという思いだった。いやはや、うまい。
ほかのキャストもみんな上手で、こんな本格的な手抜きなしのオペラをおそらくタダみたいなチケット代で鑑賞できるなんて、現代の高校生はラッキーだよ(ま、都市部に限られるが。他に京都でも鑑賞教室は行われるらしい。)。
ことしは、蝶々夫人の当たり年で、4月、6月、7月と観たが、もう一度10月にも、今度は大村博美の蝶々夫人を観ることにしている。
筋書きとしてはいろいろ議論ができる内容だが、何度観ても飽きないし、観るたびにプッチーニの音楽の巧さに気づかされる。また、日本を舞台にして日本の音楽を沢山取り入れた美しいオペラを残してくれたことに感謝する。
高校生たち、とりわけ、女学生たちはどのようにこの話を受け止めたろう。やっぱり2幕後半では泣いたろうか。それとも時代錯誤を笑ったろうか。
♪2019-097/♪新国立劇場-07