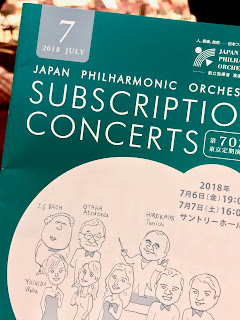2023-02-28 @みなとみらいホール
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
神奈川フィル合唱団#
大久保光哉:バリトンBr
鈴木玲奈:ソプラノSp
山本康寛:テノールTn
●ヴェルディ:歌劇「ナブッコ」から
「序曲」/「行け、わが想いよ、黄金の翼に乗って」#
●マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から
「オレンジの花は香り」#
●ヴェルディ:歌劇「椿姫」から
第1幕への「前奏曲」/「あの人から遠くはなれていては」Sp/「ああ、そは彼のひとか〜花から花へ」Sp/「乾杯の歌」Sp/Tn/#
●ワーグナー:歌劇「ローエングリン」から
第3幕への「前奏曲」/「婚礼の合唱」#
●ワーグナー:歌劇「タンホイザー」から
「夕星の歌」Br/「歌の殿堂を讃えよう」#
●エルガー:行進曲「威風堂々」第1番#
神奈川フィル専属のアマチュア合唱団。創立20年ということで、合唱団が主役のコンサート。
主としてオペラの合唱曲主体だが、ソプラノやテノールのプロ歌手の独唱も。
全て、聴き馴染んだものばかりで楽しめた。
合唱団は、名簿を数えたら凡そ女声60、男声30。
P席全部とRA・LAの一部を2人空けの拡大市松模様で並んだが、男声が上手側にちんまり収まったのはどうも迫力を欠いた気がする。
スカスカ配置だから、アマチュアといえども全員NoMaskだ。
「第九」の合唱のように高域で声を張り上げる曲がなかったせいか、全て良くできました!感じ。
定期演奏会ではなく1回券なので、久しぶりに…調べたら、2016年11月の独カンマーフィル以来だから6年3月ぶりに2階席で聴いてみた。正面最前列。
やはり1階席中央とは様子が違う。
遠い。
生々しさがない代わりにぼんやりとまとまりがいい。
評価のレンジは2-4という感じ。安全に聴けるというところか。
僕の好きな、1階席中央の中央だとレンジは1-5だ。非常に良い時もあるがひどい時もある。その僅かな5の機会を求めて席にこだわっている。
♪2023-038/♪みなとみらいホール-09