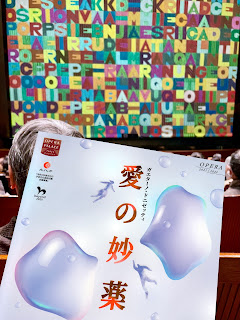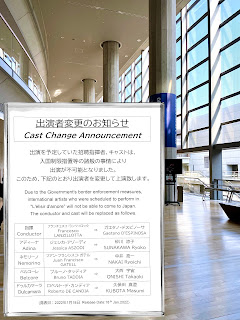2025年3月4日火曜日
新国立劇場オペラ「カルメン」
2022年2月9日水曜日
オペラ:ドニゼッティ「愛の妙薬」
2022-02-09 @新国立劇場
【指 揮】ガエタノ・デスピノーサ
【演 出】チェーザレ・リエヴィ
【美 術】ルイジ・ペーレゴ
【衣 裳】マリーナ・ルクサルド
【照 明】立田雄士
【合 唱】新国立劇場合唱団
【管弦楽】東京交響楽団
【アディーナ】砂川涼子
【ネモリーノ】中井亮一
【ベルコーレ】大西宇宙
【ドゥルカマーラ】久保田真澄
【ジャンネッタ】九嶋香奈枝
ガエターノ・ドニゼッティ「愛の妙薬」
全2幕〈イタリア語上演/日本語及び英語字幕付〉
予定上演時間:約2時間30分
第Ⅰ幕 70分
休憩 25分
第Ⅱ幕 55分
指揮のデスピノーサ&東響も「オランダ人」に引き続きの登板だ。
キャストはコロナの為に(元から出演予定の九嶋以外の)主要4役が全員日本人に代わった。
でも、それで大成功…は言い過ぎとしても、とても良かった。
何がいいかって、砂川涼子が素晴らしい。
あのふくよかで明かるく美しい声は、努力だけでは獲得できない天分だと思う。
ネモリーノ役の中井亮一にとっては歌手人生最高の大役だったと思うが、期待に応えた。
1番の聴かせどころ「人知れぬ涙」もヨシ!
もうちょっとツヤがあれば憂いも出てなお良かったが。
不満を挙げれば。
演出も美術も前回2018年公演と同じだが、前回は気づかなかったが点が今回は気になった。5年間の成長?
「文字」に拘る演出は美術面でも表れているが、「トリスタンとイゾルデ」はこの物語の契機に過ぎないのに全編にわたって「トリ・イゾ」由来の作り物がさも意味ありげに登場するのは紛らわしい。
薬売りの娘が登場するがセリフはない、歌もない。にもかかわらずなぜMaskをしているのか?
「オランダ人」の時もパントマイムの役者だけがMaskをしていた。
他にも兵士達が1幕ではMaskを。同じ連中が2幕ではNoMask。
いったいどういう整理基準なのか?
ともかく、Maskはやめてくれえ!
♪2022-016/♪新国立劇場-03
2022年2月2日水曜日
オペラ:Rワーグナー「さまよえるオランダ人」
2021年12月10日金曜日
第1946回 NHK交響楽団 定期公演 池袋C-1
2021-12-10 @東京芸術劇場大ホール
NHK交響楽団
佐藤晴真:チェロ*
チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲 作品33(原典版)*
ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」
-----------------------
カザルス:鳥の歌*
チェロ独奏もダニエル・ミュラー・ショットから佐藤晴真に交代した。
佐藤晴真は、最近よく聴くようになった
。
今年だけでも3回目。ホールにもよるけど、たいていは綺麗な音がよく響く。
ロココ風は奏者変更で、原典版に変わったそうな(尤も複数版の存在は知らなかったが。)。
編曲版「展覧会の絵」は、Hウッド版やストコフスキー版も聴いたことがある。
先日聴いたフォーレ四重奏団のピアノ四重奏版も驚嘆の音楽だった。
その昔、EL&Pの爆音演奏も生で聴いた(こういう電気増幅音楽はCDで聴く方がずっといい。)。
素材が良いからどう料理しても美味しくできるのだろう。
そして一番よく聴く編曲はラベル版だ。
耳に馴染んで安心感がある。
今日ももちろんラベル版だが、N響の演奏は、部分的には聴いたことがあるが、全曲は初めてだった。
流石にうまい。
もう、文句のつけようがない。
「展覧会の絵」の教科書のような、お手本となるような出来栄えに気分はホクホクしたよ。
いや、少しだけ不満があった。
最後のタムタムの音色が薄かったのは残念。タムタムの本来の響きはグオ〜ンという地響きのようであって欲しい。しかし、今日のタムタムは大シンバルを鳴らしたようなジャ〜ンという響きだったよ。