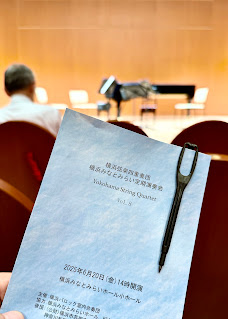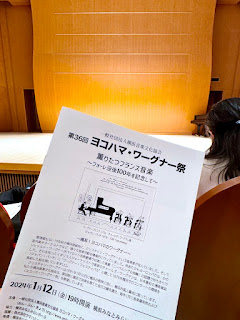2023-10-09 @新国立劇場
【指 揮】沼尻竜典
【演 出】粟國淳
【美 術】横田あつみ
【衣 裳】増田恵美
【照 明】大島祐夫
【振 付】伊藤範子
【舞台監督】髙橋尚史
●修道女アンジェリカ
【アンジェリカ】キアラ・イゾットン
【公爵夫人】齊藤純子(マリアンナ・ピッツオラートの代役)
【修道院長】塩崎めぐみ
【修道女長】郷家暁子
【修練女長】小林由佳
【ジェノヴィエッファ】中村真紀
【オスミーナ】伊藤晴
【ドルチーナ】今野沙知恵
【看護係修道女】鈴木涼子
【托鉢係修道女1】前川依子
【托鉢係修道女2】岩本麻里
【修練女】和田しほり
【労働修道女1】福留なぎさ
【労働修道女2】小酒部晶子
-------------------------------------
●子どもと魔法
【子ども】クロエ・ブリオ
【お母さん】齊藤純子
【肘掛椅子/木】田中大揮
【安楽椅子/羊飼いの娘/ふくろう/こうもり】盛田麻央
【柱時計/雄猫】河野鉄平
【中国茶碗/とんぼ】十合翔子
【火/お姫様/夜鳴き鶯】三宅理恵
【羊飼いの少年/牝猫/りす】杉山由紀
【ティーポットト】濱松孝行
【小さな老人/雨蛙】青地英幸
プッチーニ/修道女アンジェリカ &
モーリス・ラヴェル/子どもと魔法
全1幕〈イタリア語・フランス語上演/日本語及び英語字幕付〉
上演時間約2時間25分
修道女アンジェリカ
全Ⅰ幕65分
-------------------
休憩35分
-------------------
子供と魔法
全Ⅰ幕45分
❶Wビルの1本目はプッチーニの「修道女アンジェリカ」。
生舞台は初めて。放送(録画)で、内容は承知しているので、あまり期待もせず臨んだが、案の定、楽しめない。
これは歌唱・演技・演出・舞台美術の問題ではなく、そもそもの原作のあちこちに疑問を感ずるので、どうにもしようがない。
中でも、修道院で7年間、事実上軟禁生活を強いられているアンジェリカを叔母の公爵夫人が尋ねてきたところから、問題噴出。7年前に引き裂かられ我が子が2年前に亡くなっていることを聞かされ、希望を失ったアンジェリカは毒を仰ぐ。その途端。自死は大罪であることを思い出し神に許しを乞う。
1番の問題は、毒の回った彼女の前に子供が現れる(原作のト書きでは黙役の金髪の子が現れる。現にそういう演出の舞台を録画で観ている。)。
これが神の奇跡なのか、それが問題だ。
大抵の解説には奇跡であると書いてあり、公演プログラムも同様。しかし、演出者の弁では、そこは曖昧で、実際舞台でも子供を登場させず、アンジェリカの身振り手振りで子供の存在を感じさせる。そういう演出が意図するのは、神の奇跡と思いたい人は思ってもよし。幻覚と受け止めることも否定しない。とややアンフェアな態度だ。
しかし、カトリックが自死を禁じている以上、神の恩寵である「奇跡」は起こってはならないのだ。
それを原作では奇跡と描いているのが大きな問題だ。
あるいは、僕の見立てのように(演出者にもそのような意図が半分は見られる)、薬物中毒者の死に際の幻覚であるとすれば、事件の発端から最後まで、実につまらない女性のつまらない短い一生を描いただけのうすっぺらな物語である。
オペラとしての出来は、如上の理由でキアラ・イゾットンの熱演にも関わらず楽しめなかった。
よく似た話が1955年スペイン映画「汚れない悪戯」だ。主題歌の「マルセリーノの唄」でお馴染みだ。
12人の修道士が暮らす修道院の前に男の赤子が捨てられた。慣れない男たちが我先に争うようにその子マルセリーノを慈しみ育てるが、5歳になった時、屋根裏部屋の磔のキリスト像と対話を始め、厨房からパンや葡萄酒を盗んで像に供える(汚れなき悪戯)。おかしいと思った修道士たちはマルセリーノの後をつけ、屋根裏部屋に上がり、彼とキリスト像の対話を目にすることになる。1番の望みは?とキリストに問われ、マルセリーノは「ママに会いたい」と答える。
その結果がどうなるか、覗き見をしていた修道士たちには分かっていても、神の大いなる奇跡の前に立ち尽くすばかりだった。
この話では、ママは既に亡くなっている。マルセリーノは生きており、純粋で篤い信仰心を持っている。そこに神の恩寵としての奇跡が起こるのだ。
僕はクリスチャンじゃないし、そもそも宗教を疑問視しているが、信仰心(仰ぎ見る・信ずる心)は大切ではないかと思っている。だから、このようなマルセリーノに起こった奇跡を信じたいと思い、この映画を観る度に(いや、思い出す度に)ハラハラと泣けてしまう。
プッチーニはもっと台本を吟味すべきだった。
❷「子供と魔法」
全く期待していなかった。子供の絵本みたいな話に付いてゆけそうにもない。これも舞台は初めての経験だった。録画ディスクは目を通しているが、子供さえ楽しめないだろう…と思っていたが、今回の演出、というより、舞台美術と衣装には驚かされた。プロジェクター投影の画像と作り物が見事に美しく、遊び心に溢れている。
音楽はラヴェルだから、つい、口ずさみたくなるようなものではないが、つい、頬が緩むような舞台だった。
お母さんが影絵だけで最初と最後に登場し、魔法の世界の扉の役を果たしていた。演じ歌った歌手にとっては残念だったかもしれないが、演出的には良いアイデアだった。
2作とも新制作だが、少なくとも「子供と魔法」は再演を期待したい。
♪2023-170/♪新国立劇場-16