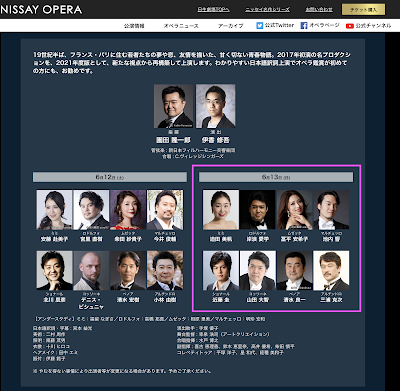2023-07-08 @サントリーホール
広上淳一:指揮
日本フィルハーモニー交響楽団
合唱:東京音楽大学
児童合唱:杉並児童合唱団
カニオ(座頭/道化師役)
⇒笛田博昭
ネッダ(女優・カニオの妻/コロンビーナ役)
⇒竹多倫子
トニオ(のろま役の喜劇役者/タデオ役)
⇒上江隼人
ベッペ(喜劇役者/アルレッキーノ役)
⇒小堀勇介
シルヴィオ(村の若者)
⇒池内響
農民:岸野裕貴、草刈伸明
( A/B )はAが劇中の役、Bが劇中劇の役
レオンカヴァッロ:歌劇《道化師》
(演奏会形式オペラ)
「道化師」は、深く考えなければ単純な物語だけど、台本の欠陥か、作者の知恵が深すぎるのか、よく分からないところがある。この点については後記することにしよう。長くなりそうだから。
最近、どのホールも響が良い。エアコンがんがん入れているからか、お客が軽装になったからか分からないけど、サントリーでさえ全く不満はなかった。
横浜定期を振り替えてもらったので、好みの席ではなかったけど、まあ、許容範囲で、オペラ向きに舞台からも近くて良かった。
演奏会形式だ。それも全員正装で譜面台の後ろに立つ。もちろん多少の身振り手振りはあるけど、簡易な舞台装置もなく、小道具もなし。照明も通常のコンサートと同じ。
東フィルや神奈川フィルのオペラの場合、演奏会形式といっても、スカーフを纏うとか、小道具を手にするとかそれなりの役作りがあり、照明も工夫されているが、こんなにすっからかんに割り切ったのは初めてだ。
しかし、これはお客の方も割り切れば良いので、ひたすら、歌唱を、音楽を味わうにはこれもありだろう。
歌手陣の中では、やはり主役の笛田博昭が声量も豊かだし、歌いながらの演技という面でも一番良かった。彼は藤原歌劇団でこの役を演じているから、自家薬籠中のものとしているのだろう。
今日は、大勢の合唱団もP席を使わず舞台最後列に並んだので、跳び箱二段重ねのような高い指揮台に立った広上センセが、踊って落ちやしないかと心配だったが、いつもながら小さな身体を目一杯大きく使ってエネルギッシュに指揮をしているのはなかなか形が美しいなと感心をした。
休憩なし70分が予定されていたが、実際は幕まで80分くらいだった。
最後のセリフ「喜劇は終わった」を、今日はカニオが言った。トニオが言う演出もあり、先日家で観た藤原歌劇団のビデオではトニオだった。念の為、我がコレクション計4枚を終幕のところだけ再生したら、2対2だった。
僕が演出家なら、当然、トニオのセリフにするけどな。
なぜなら、オペラの冒頭、幕の前で(今日は幕がなかったが)トニオが前口上を述べる。これがこれから始まるオペラへの口上なのか、オペラの中で演じられる劇中劇に対する口上なのかはっきりしない。いや、はっきりしていて、前者が正解だと思うが、演出によっては、劇中劇でトニオが演ずるタデオ役の衣装を身につけて口上を言うものもあるからだ。しかし、そのように解してはオペラ全体の時制が混乱してしまう。
だから、冒頭のトニオの口上は、トニオではなく、もちろんタデオでもない、レオンカヴァッロ本人の口上だと考えるべきだ。そしてこの時制はいわば時を超越した《超越》時制だ。
幕が開くと、オペラ《劇》の始まりだ。カニオと妻ネッダは険悪になるがカニオは怒りを抑え、間も無く始まる芝居の準備をする。以上が《劇》第1幕。
第2幕が始まると今度は《劇中劇》の世界だ。偶然にも《劇》第1幕と同じドラマが展開され、カニオは劇中であることを忘れ妻とその恋人を殺めてしまう。
とんでもないことをしてしまった、と我に帰ったのが《劇》の世界。その混乱をおさめるセリフが「喜劇は終わった」だ。そのセリフはどの時制から発せられるのか?
「喜劇」が《劇中劇》を指しているなら、《劇》の時制から。
「喜劇」が《劇》を指しているなら、《超越》時制からと言うことになる。
しかし、《劇中劇》は我に帰った時点で《劇》になるのだから、「喜劇」とは《劇》そのものであり、それを「終わった」と宣告できるのは、オペラの冒頭「時」を超越して前口上を述べた時制と同じでなければならないはず。つまり、「喜劇は終わった」は、《劇中劇》ではタデオを演じ、《劇》中ではトニオを演じていた、その実正体はレオンカヴァッロ自身ではないか、と思うのである。
…と仮説を立てて、次回観るときの観察視点としよう。
♪2023-120/♪サントリーホール-15