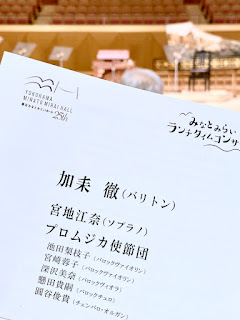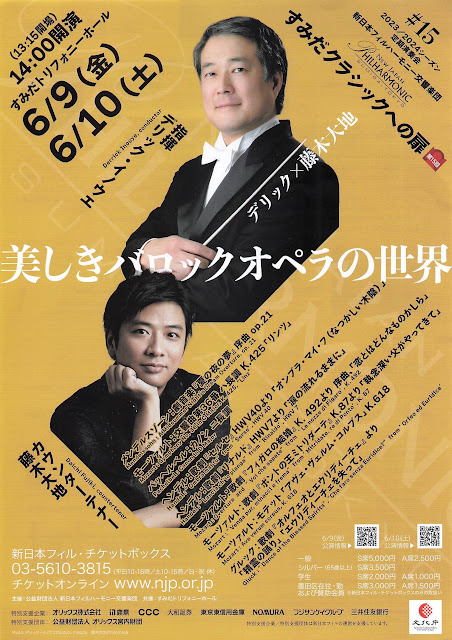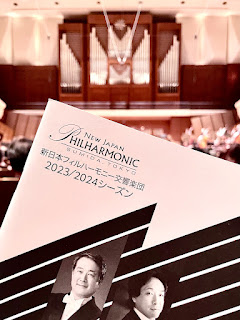2025-05-24 @ミューザ川崎シンフォニーホール
横島勝人:指揮
青山シンフォニーオーケストラ
町田正行:チェロ*
モーツァルト:交響曲第25番ト短調 K.183
エルガー:チェロ協奏曲ホ短調 Op.85*
ドボルザーク:交響曲第8番ト長調 OP.88
-----------------------
カザルス:鳥の歌*
ドボルザーク:スラブ舞曲第10番
ヘンデル:ラルゴ
という感じで、たぶんアオガク関係者のOBオケだろうなと思っていたが、事前に調べなかったので情報はなく、本番のプログラムにも何に書いてない。帰宅後NETでHPをみて初めて正体が分かったが、予想どおりだった。
アオガクOBオケが母体で、今は、広く同好の士を募っているみたいだけど、青山と名乗る以上、全く無関係では入りにくいだろうな。
定期演奏会は年に1回というから、まあ、多くの弱小アマオケの一つなんだろうな。
チケットを買った当時は、そういう事情も知らなかった。
偏に、エルガーのVc協を聴きたかったからだ。
過去平均では、2.5年に1回の割で聴いている。前回が22年1月都響だったので、まあ、平年ベースなのだけど、最近、この胸を掻きむしられるようでつらくてたまらない激しい音楽に飢えている?というか、なかなか決定版が聴けないのだ。
それで、青山の何たるかはどうでもいいから、聴くことにした。
今日、初めて聴いたオケだが、まずは全体が高水準。
指揮者も初めてだが、ちょいちょい見せる独自解釈が聴き慣れたものとは違うというだけで、あれも悪いとも言えないだろう。ただ、エルガーは、なんかまとまりに欠け求心力がなかった。ドボ8に至れば、一層入り込めなかった。
その、エルガーだが、独奏者はもちろん初めて。華々しい経歴もないけど、主として指導者として活躍をしている人らしい。このオケのトレーナーでもあるという。
久しぶりにスポットライトを浴びたのだろうけ、いやはや上手なものだ。何より、音が美しい。はじめて宮田大を聴いた時の驚きを彷彿とさせる美音の連続。
しかし、いつ、誰を聴いても、問題は、独奏がオケに負けているということだ。
これは、もう、どうにもならないと思うよ。
ピアノ以外、オケと対等に鳴らすなんてできない。
PAを使うのは邪道だけど、協奏曲ではやむを得ない。
思い切って、マイクで拾って生々しい音を増幅してみてはどうだろう。ギターではそういう試みを聴いたことがある。チェロでも(超現代曲ではあったが)PAを使った協奏曲を聴いた。
そりゃあもう安心だよ。
ヤニの飛び散る音を拾って増幅してくれえ!
♪2025-067/♪ミューザ川崎シンフォニーホール-05