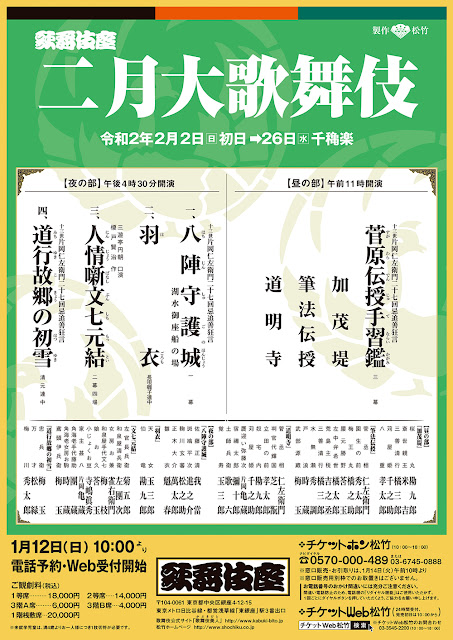2022年3月18日金曜日
令和4年3月歌舞伎公演『近江源氏先陣館-盛綱陣屋-』
2021年10月21日木曜日
10月歌舞伎公演「通し狂言 伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)」
2021-10-21 @国立劇場
近松徳三=作
通し狂言「伊勢音頭恋寝刃」(いせおんどこいのねたば)
三幕七場
国立劇場美術係=美術
序幕
第一場 伊勢街道相の山の場
第二場 妙見町宿場の場
第三場 野道追駆けの場
第四場 野原地蔵前の場
第五場 二見ヶ浦の場
二幕目
第一場 古市油屋店先の場
第二場 同 奥庭の場
福岡貢 中村梅玉
藤浪左膳/料理人喜助 中村又五郎
油屋お紺 中村梅枝
油屋お鹿 中村歌昇
奴林平 中村萬太郎
油屋お岸 中村莟玉
徳島岩次実ハ藍玉屋北六 片岡市蔵
藍玉屋北六実ハ徳島岩次 坂東秀調
今田万次郎 中村扇雀
仲居万野 中村時蔵
ほか
2015年に梅玉の主演で国立劇場では初めて通し狂言としてかけられたのを観た。
今回は、同じく「通し」といっても初演時に比べて一幕少ない。
コロナ以降の芝居は、概ね短縮形になっている。
役者も梅玉の他は莟玉(当時は梅丸)が同じ役で出ている他は多分全員変わっている。
歌舞伎としては色々見処(二見ヶ浦の場、油屋奥庭など)があるが、主人公が妖刀のせいにして殺される程の罪もない者8人ばかりに斬りつけ、その部下が「切れ味お見事!」と持ち上げて幕という構成や演出にちょいと疑問あり。
返り血を浴びた梅玉の見得などは残酷美でもあるが陰惨な印象が残った。
中村莟玉が同じ役で出ている(前回は10代だった!)が、6年経って女の色っぽさが益々磨かれたようで同慶の至り。
梅枝もいい女方だし、いずれは父時蔵が演じた大きな役の仲居万野を演るようになるのだろう。
今回は歌昇が生涯初めての女方だそうだが、滑稽な味も出して初めてとは思えない良い出来だった。
♪2021-113/♪国立劇場-08
2020年10月7日水曜日
10月歌舞伎公演第1部
2020-10-07 @国立劇場
●ひらかな盛衰記
梶原源太景季 中村梅玉
腰元千鳥 中村扇雀
梶原平次景高 松本幸四郎
母延寿 中村魁春
ほか
●幸希芝居遊
久松小四郎 松本幸四郎
金沢五平次 大谷廣太郎
二朱判吉兵衛 中村莟玉
三国彦作 澤村宗之助
ほか
文耕堂ほか=作
●ひらかな盛衰記(ひらがなせいすいき)
-源太勘当-梶原館の場
鈴木英一=作
●幸希芝居遊(さちねがうしばいごっこ)
常磐津連中
国立の歌舞伎は1月公演以来だ(2月は休演月。3月以降はコロナ休演)。
国立劇場ではコロナ再開後の興行形態が、寄席・文楽共々歌舞伎も変わった。
1日の公演数を多く(2公演)・短時間にして料金も少し安めだけど全公演を観たいから結局C/Pは悪い。
しかし、歌舞伎公演に関しては、僕の<指定席>と言っていい程こだわって取っていた2階最前列花道寄りは従来1等A席だったが、再開後は1〜3階が各1〜3等席と決められたので、嬉しいことに我が<指定席>2階最前列が2等席になって料金は半額以下となった。
1日2公演制になったが、両方観ても従来より安価だ。
逆に1階席ファンには気の毒なことに前より高くなった。
第1部は2本立て。
「ひらかな盛衰記」から”源太勘当”。「ひらかな〜」といえば、圧倒的に”逆櫓”の上演機会が多く、こちらは何度も観たが”勘当”は初めて。
宇治川の先陣争いでわざと勝ちを譲った梶原源太景季/梅玉を武家の建前から母/魁春が勘当するという話だが、源太の弟の小憎らしい平次/幸四郎や源太と恋仲の千鳥/扇雀が絡み、悲話だが笑いどころもあって面白い。
扇雀が声も姿も若々しいのに驚いた。
幸四郎は剽軽役も巧い。
2本目・新作「幸希芝居遊」でも幸四郎が主役で登場し、多くの有名な歌舞伎の見処を繋ぎ合わせて見せてくれる。
全篇に幸四郎の歌舞伎愛が溢れていて胸熱に!
♪2020-060/♪国立劇場-07