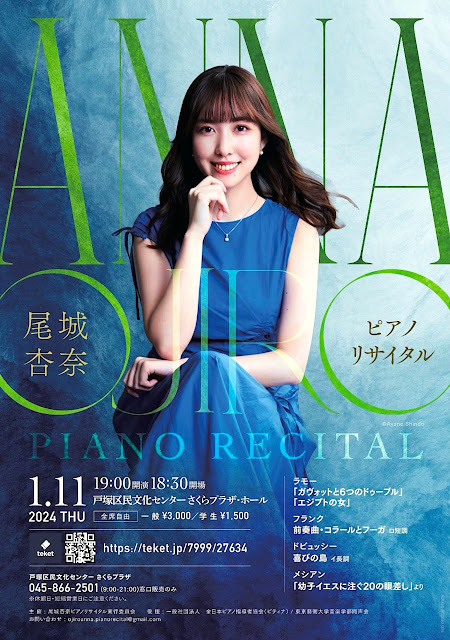2016-10-10 @みなとみらいホール
シルヴァン・カンブルラン:指揮
マルティン・シュタットフェルト:ピアノ*
読売日本交響楽団
ラモー:「カストールとポリュックス」組曲から
「序曲」・「ガヴォット」・「タンブラン」・「シャコンヌ」
モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番*
シューベルト:交響曲第8番「グレイト」
---------------
アンコール
ショパン:練習曲 作品25-1「エオリアン・ハープ」*
ラモーの作品は初聴き。初演が1737年。評判が悪かったので54年に改訂したとある。ハイドンが初演を聴いたとしたら5歳位。モーツァルトが生まれたのは改訂版の完成より後だ。ま、そんな時代の音楽なので、サロン音楽みたいに軽やかに耳に入って来るけど、やはり最初の曲って、どうもオケのエンジンは暖機運転みたいだ。
ピアノのマルティン・シュタットフェルトは初めて。04年にゴールドベルク変奏曲でCDデビューしたことからか、「グレン・グールドの再来」と評される、と解説に書いてあったが、まあ、見た目も似ているし、低いピアノ椅子に座って弾く姿勢もそんな感じはした。
本物ならどんな弾き方をするか知らないけど、シュタットフェルトのピアノはごく普通の?モーツァルトに聴こえた。
因みに、グレン・グールドのバッハやベートーベンなどは好きだけど、彼が弾くモーツァルトのピアノソナタ第11番(トルコ行進曲付き)を初めて聴いた時につんのめって、遊んでるのじゃないか、と腹立たしく思ったので、それ以来、グレン・グールドの弾くモーツァルトはCDを買わないことにしている(ほとんど出ていないけど。)。
で、このピアノ協奏曲第15番は、CDは全27曲セットがあるので過去に聴いたことがあったけど、20番台の作品のように、今日はこれを聴いてみたいと思わせるような魅力は感じたことがないので、多分、ナマで聴いたのは初めてだったと思うけど、やはり、印象が希薄なままスルーっと抜けていった。
ラモー、モーツァルト、シューベルトというプラグラムそのものがなんだかピンとこないので、聴く態度が定まらないという感じだ。
超大曲でもないし、超絶技巧曲でもなさそうだし、ピアニストには悪いが、消化試合というか、映画で言えば、その昔のプログラムピクチャーのような気がして、聴く側に緊張感が生まれないのは困ったものだ。
で、一番楽しみにしていたのがシューベルトの第8番だ。
「楽しみ」というより、強い「関心」かな。
というのも、昨日、ズービン・メータ指揮ウィーン・フィルで聴いたばかりだったから(同じ曲を翌日聴くことになるとはなんという巡り合わせだろう。)。
昨日の印象では、世界の一流オケの実力をナマで聴いた結果は日本の一流オケも十分世界に通用するのではないか、と思ったのだが、さて、読響はどうか。
かなり肉薄していたと思う。
どこが違うだろう、とずっと耳を澄ませていたのだけど、管と弦が強奏で重なる場所などで透明感に欠ける。あるいは、弦の高音域での透明感に欠ける。つまりは、ときどき管弦楽にざわつきが混じることがある。それも、いわば、敢えてアラ捜しをしながら聴いているので感ずる程度のものだ。
だから、今日の読響を聴きながら、やはり、うまいものだと感心した。
でも、ウィーン・フィルとの僅かな差(これはN響や都響でもいつも感じていることだけど)。これが容易なことでは埋められないのだろうと思う。
でも、この差を聴き分けたくてチケット代4倍も5倍も支払いたくはないな。
♪2016-138/♪みなとみらいホール-35