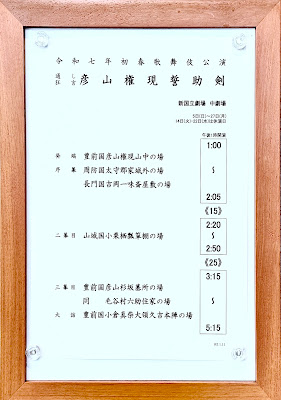2025-01-14 @サントリーホール
レナード・スラットキン:指揮
東京都交響楽団
金川真弓:バイオリン*
シンディ・マクティー:弦楽のためのアダージョ(2002)
ウォルトン:バイオリン協奏曲*
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 op.27
金川真弓を初めて聴いたのは21年2月の都響との共演だった。鮮烈な印象を受けた。以来、4年間で12回。平均1年に3回も聴くなんてソリストでは最高頻度かも。しかも、うち6回は都響だ。実際の共演はもっと多いかもしれない。
呼吸の合ったコンビだとしても個人的にはウォルトンのVn協は初聴きで、あまり楽しめる音楽ではなかった。
それにサントリーは独奏楽器がイマイチ響いてこない。
しかし、相変わらず、Vn界の弥勒菩薩は佇まいが美しい。
Encを聴きたかった。何度もCCで出入りしたが、遂にやらずじまいだったのは、後に長尺が控えていたからだろうな。
冒頭のシンディ・マクティー「弦楽のためのアダージョ」も初聴きで、穏やかな弦楽Ensだ。さあ、ゆっくり寝てください、と言わんばかりで、そのうち本当に寝てしまったが、不思議なことに終曲の拍手で目が覚めるということは一度も経験していない。必ずその手前で覚醒するのは不思議だが、赤ちゃんは寝ていても音は聴いているようで、大人も同様なのだろう。
そのマクティー夫人も登壇して拍手喝采を受けたが、後で知ったが、この人、ストラッキンの奥さんだとはびっくりした。2人ともずいぶん高齢で結婚したんだ。
マクティーの作品は22年5月のやはり都響AとB(同一プログラム)で聴いているのだけど、その時もVn独奏者として金川真弓が登場しているのは、不思議な偶然。
メインがラフマ交響曲第2番。
3つの交響曲の中でダントツに聴く機会が多い。毎年1回以上聴いている勘定だ。その割になかなか共感できる演奏は少ない。でも今日の演奏は良い方だった。
都響の16型の印象は頗る悪く、うるさい、やかましい、バラバラと感ずることが多いが、スラットキンはこの曲を得意としているとか…。これまでN響としか聴いたことがなかったが、かなり、彫琢を施したか、あまり乱れもなく好首尾だったと思う。
いつも疑問に思い、いまも解けないでいるのは、一番美しい第3楽章の主題の美旋律。あれは、どこか他の曲でそっくりなのを聴いているような気がするが、思い出せない。
♪2025-005/♪サントリーホール-01