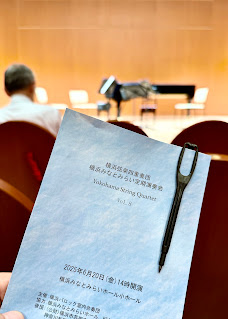2025-06-29 @東京オペラシティコンサートホール
セバスティアン・ヴァイグレ:指揮
読売日本交響楽団
児玉隼人:トランペット*
ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ヴァインベルク:トランペット協奏曲変ロ長調 作品94*
サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 作品78「オルガン付き」
-----------------
シャルリエ:36の超絶技巧練習曲から第1番*

最初に躓くと、立て直しが容易ではない。中盤以降面白くはなったが、とても読響とは思えない。
2曲目。ちょうど1W前のM.ブルネロがプログラムの半分をヴァインベルクの作品に充てていたが、最近、ちょいちょいこの作曲家を聴く機会がある。
その初聴きのTp協が結構面白くて気分を取り直した。
作品の面白さと以上に、独奏した16歳の児玉隼人の妙技に唸らされた。
楽器と身体は一体になって、道具を操るというより、彼が歌ったままが楽器から出ているという感じで、これにはびっくり。
後半、サン=サーンスのガン付き。ま、どのオケが誰の指揮でやってもまずは楽しめる作品だけど、ここへきて読響は弦の透明感とブラスの凄まじさが相まって、上出来だった。
ただし、今日は、振替の右翼席で、目線の先はVaの最後列とCb群だ。旋律を弾くVn1は遥か下手で、時々リズムの刻みがずれているように聴こえた。
それで読響の力演にもかかわらず三半規管が故障しているような気分にさえなった。
♪2025-086/♪東京オペラシティコンサートホール-09